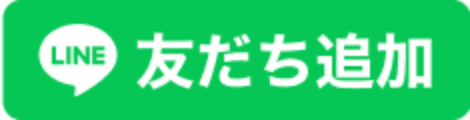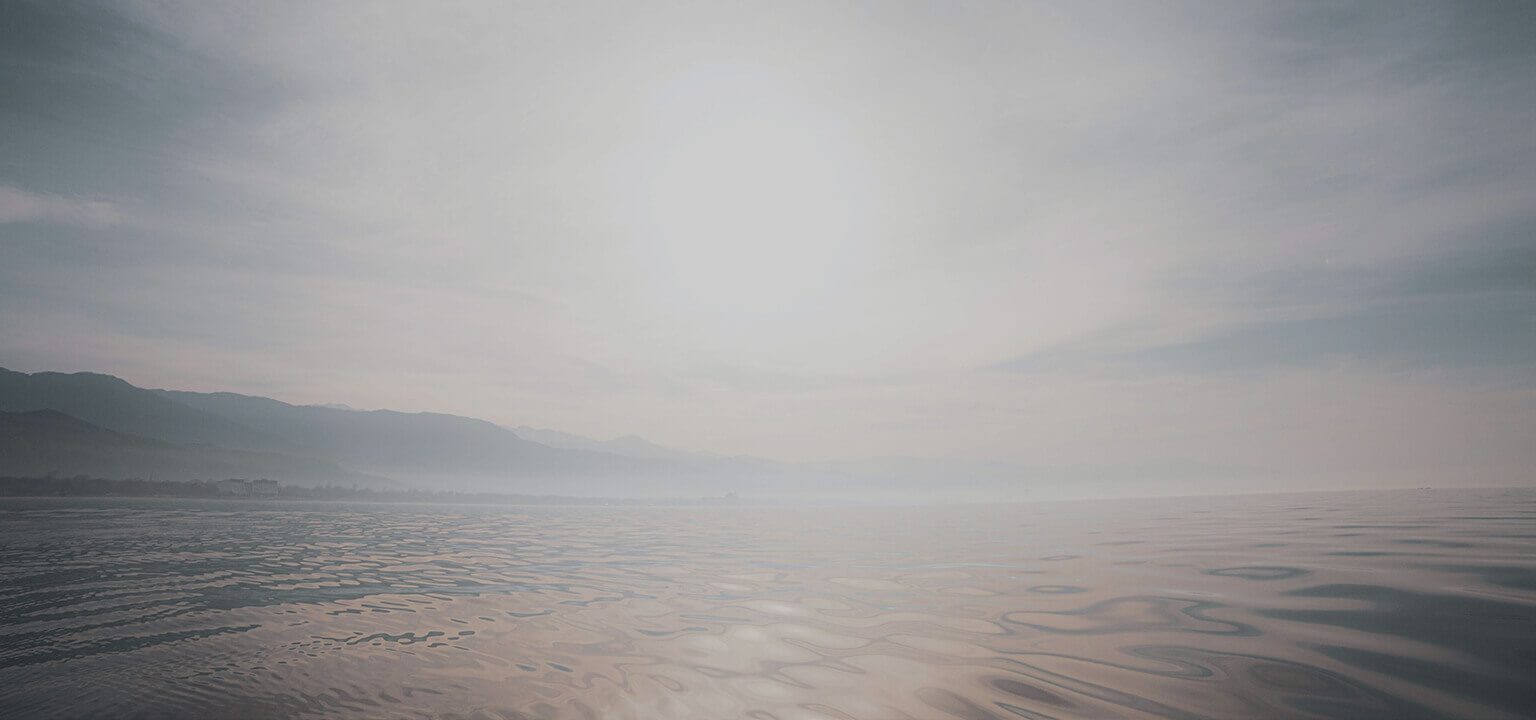ボイトレの基礎5トーンスケールで音楽力をレベルアップさせよう!

5トーンスケールは音階を使った、ボイトレの発声練習パターンのひとつです。
スケールとは、日本語で言う音階のこと。
いちばん分かりやすいのが「ドレミファソラシ」、この音の流れもスケールと言います。
このスケールを使ったボイトレをすると、正確な音程がとれやすくなるほか、発声や呼吸などボイトレの基礎となる部分を鍛えることができます。
曲を使った練習ももちろん大切ですが、基礎を習得するならスケール練習がおすすめです。
なぜなら、音が縦横無尽に行きかう曲よりもシンプルで分かりやすいから。
そのあたりも含めて、今回は5トーンスケールをはじめとした、スケール練習について解説していきたいと思います。
ボイトレの基本5トーンスケールとは

冒頭でもお話したように、スケールとは音階のことです。
音階にもいくつか種類があり、
半音階
短音階(マイナースケール)
長音階(メジャースケール)
などがあります。
また、ボイトレで使うスケールは5トーンスケールだけでなく、2トーンスケール、オクターブスケールなど、いろいろなパターンがあるんですよ。
その中のひとつ、5トーンスケールは、「ドレミファソファミレド」の音形のスケールを使った練習のことをさします。
練習方法を簡単に説明すると、「あー」の発音で、「ドレミファソファミレド」の音に合わせて歌います。
スケールは半音ずつ上がり、徐々に高音へ向かっていき、ある一定の音まで行ったら今度は半音ずつ下がってくるというものです。
5トーンスケールをボイトレで練習するメリット

ボイトレで、5トーンスケールを練習するメリットをみてみましょう。
まず、音程を正確にとれるようになります。
また、歌や曲は、ひとつの音では成り立っていませんよね。
高い音や低い音、いくつもの音が連なってメロディができています。
メロディは曲にもよりますが、あちこちに音が飛びながら移動しているように感じませんか。
しかし、これは音楽すべてにおいて言えることですが、複雑に見えるメロディも、紐解いていくと、あらゆるスケールの組み合わせでできているのです。
少し難しい話かもしれませんが、音楽はスケールの組み合わせでできている、ということだけ分かれば、あらゆるパターンのスケール練習をすることの意味が見えてきませんか。
ボイトレでスケール練習をしておけば、音飛びが多い曲、なめらかに音が上がっていく曲など、どんなパターンの曲に出会っても、そのパターンや感覚、そして音程をつかみやすくなるのです。
もちろん、スケール練習だけしていればよいわけではなく、そこにさまざまなテクニックや表現が加わっていくわけですが。
他にも、5トーンスケールの練習をするときには、姿勢、発声、呼吸など意識することがあります。
それらボイトレの基礎となる部分も、同時に習得できることも5トーンスケールを練習するメリットです。
ボイトレ実践!5トーンスケールの練習方法

5トーンスケールのボイトレ方法は、先ほど説明したとおり、
① 「あー」と発声しながら「ドレミファソファミレド」の音階を歌う
② 半音ずつ上がっていき、声の限界値に達したら半音ずつ下がってくる
以上です。
しかし、ただ発声していても意味がありません。
次に説明する、チェックポイントにあげたことを意識して練習しましょう。
ボイトレの5トーンスケールでチェックするポイント
ボイトレで5トーンスケールを練習する際は、次のことを意識して、できているかどうかチェックしてみてください。
喉仏の位置
喉仏の位置を意識しましょう。
喉仏が上がると、喉は締まってしまいます。
逆に、下がり過ぎても喉は締まってしまいます。
発声におけるちょうどよい位置を見つけましょう。
吐く息の量
吐く息の量は、多すぎれば声が枯れてうまく出せません。
かと言って、少なすぎても息が続かないなどでてきてしまいます。
また、5トーンスケールでは、「ドレミファソファミレド」を一息で発声しますが、吐く息の強さは一定であるのが理想です。
声が上がったり下がったりするときに、息の強さや量を変えないように意識して練習しましょう。
喚声点の位置
喚声点とは、地声から裏声に変わるポイントのこと。
スケールが上がっていき、地声では出せない音域に到達したとき、声が裏返ったりかすれたりします。
この喚声点を、スムーズに移行できるのが理想的です。
喚声点をなくすボイトレ方法もいろいろあるので、そちらもプラスすると効果的でしょう。
また、5トーンスケールをする中で、自分の苦手も見つけてください。
そうすれば、自分にはどんなボイトレが必要なのかが分かってきます。
苦手を見つけるときは、
・裏声が上手く出ない音はどれ?
・音と音の切り替えができていない場所はどこ?
・喉が締まってしまう音域は?
など、注意して見てみましょう。
歌いながら考えるのが大変なときは、録音をしておきましょう。
自分の声を客観的に見ることができるので、いろいろなことに気付きやすくなりますよ。
ボイトレで5トーンスケールをするときに注意したいこと

ボイトレで、5トーンスケールをするときに意識したいことを説明しましたが、今度は、注意したいことに触れていきます。
ウォーミングアップ
5トーンスケールに限らず、ボイトレをするときにはウォーミングアップをしておきましょう。
肩を上げたり下げたり、肩に腕をのせて回したり、体をリラックスさせて力を抜きます。
それから、
・姿勢を整える
・表情筋をほぐす
・肩、首のストレッチ
・腹式呼吸の準備
など、これからたくさん発声をしていくので、体の準備はしっかりしておいてくださいね。
また、
・こまめな水分補給
・無理な音域は無理をして出さない
・長時間練習しない
・リラックスして行う
など、これらのことにも十分注意してください。
5トーンスケール以外のボイトレスケールパターン
ボイトレには、5トーンスケール以外にもいろいろなスケールのパターンがあります。
・2トーンスケール
スケールパターン「ドレドレドー」
・3トーンスケール
スケールパターン「ドレミレド」
・4トーンスケール
スケールパターン「ドレミファミレド」
そして、
・5トーンスケール
スケールパターン「ドレミファソファミレド」
・オクターブスケール
スケールパターン「ドミソドソミド」
スタート地点の「ド」から1オクターブ上の「ド」に向かい、1オクターブ上の「ド」までいったらスタート地点の「ド」に戻ってきます。
すべてのパターンは、半音ずつ上がっていき、半音ずつ下がってきます。
いろいろなパターンのスケールを活用して練習をしてみてください。
5トーンスケールの発声をボイトレで使うあの言葉に変えてみる

5トーンスケールでは、発声するときの言葉も変えてみましょう。
ボイトレでは、おなじみのテクニックばかりですよ。
・ハミング
・リップロール
・タングトリル
・グッグ
・ネイネイ
・ヤイヤイ
・あー
・はー
・まー
など。
ハミングは鼻腔共鳴の感覚をつかみやすく、高音もだしやすくなる。
リップロールやタングトリルは、表情筋や舌をほぐしたり、喚声点をなめらかにするなど、それぞれに効果がたくさんありますよね。
目的に合わせて、いろいろな言葉を試してみてください。
5トーンスケールで5オクターブ出るようになる?
ボイストレーニングでよく使われる「5トーンスケール」は、音域を広げるための基本的な練習法です。短い音の上昇と下降を繰り返すことで、声帯の柔軟性を高め、地声と裏声のつながりをスムーズにしてくれます。
では、この練習を続けることで、憧れの5オクターブボイスを出せるようになるのでしょうか?
ここでは、5オクターブという音域の実際と、そこへ近づくためのポイントを詳しく解説します。
5オクターブとはどのくらいの音域?
5オクターブとは、1つの音を基準にその5倍の高さ(または低さ)まで声が出せる音域を指します。たとえば、ド(C)を基準とした場合、5オクターブ上のドまで出せるということ。
一般的に、男性の平均音域は2〜2.5オクターブ、女性で2.5〜3オクターブほどといわれています。つまり、5オクターブというのは並外れた音域であり、プロシンガーでも限られた人しか到達できません。
とはいえ、トレーニング次第で音域を少しずつ広げ、3〜4オクターブを目指すことは十分に可能です。その基礎として効果的なのが、5トーンスケールなのです。
5トーンスケールが音域拡大に効果的な理由
5トーンスケールは、5音だけを使って上昇と下降を繰り返すシンプルな練習法です。
しかし、この短い音の動きの中に「声帯の伸縮」「息のコントロール」「共鳴の移動」といった発声の基礎がすべて含まれています。
つまり、5トーンスケールを続けることで、喉に力を入れずに音を上下させる感覚が身につくのです。結果として、地声から裏声までの切り替え(換声点)がスムーズになり、自然に音域が広がります。高音に無理なく届くようになり、安定した発声を保ちながら、より豊かな表現力を手に入れることができます。
5オクターブを出すために必要なトレーニング要素
5オクターブを出すには、ただ高い音を練習するだけでは足りません。
重要なのは、喉の柔軟性と声帯のバランス、そして息の支えを保つ筋力です。特に「ミックスボイス」を習得することがカギになります。ミックスボイスとは、地声と裏声を自然に融合させる発声法で、喉に負担をかけずに高音域へスムーズに移行できます。
さらに、共鳴(レゾナンス)を意識することで、響きを上方向に導き、より伸びやかな音が出せるようになります。5オクターブという極限の音域は簡単ではありませんが、ボイトレを通じてその「土台」を確実に築くことができます。
ミックスボイスについては下記で詳しく解説しています。こちらも是非ご覧ください。
ミックスボイス習得のカギ!そのメリットとトレーニング法を徹底解説
女性が5オクターブに近づくためのポイント
女性の場合、もともと声帯が短く薄いため、高音域は出しやすい傾向にあります。
ただし、喉を締めて無理に出そうとすると声帯を痛める原因にもなります。5トーンスケール練習では、喉を開き、息を流しながらリラックスして声を出すことが大切です。また、ホルモンバランスの変化により声帯の状態が変わりやすいため、体調に合わせたトレーニングも必要です。
女性が5オクターブに近づくには、「喉の力を抜く」「呼吸を深くする」「共鳴を上に導く」の3点を意識することがポイント。正しい練習を積めば、無理のない範囲で驚くほど高い音域が出せるようになります。
5オクターブを目指すなら、正しい発声フォームを身につけよう
5オクターブの音域を目指すためには、単に高音を出すだけでなく「正しい発声フォーム」を習得することが欠かせません。喉や息の使い方、姿勢や体の支えなど、声を出すための基礎を整えることが最も大切です。ここでは、5トーンスケールをより効果的に活かし、オクターブの幅を広げていくために意識したいポイントを紹介します。
腹式呼吸で息の支えを安定させる
腹式呼吸は、5オクターブに近づくための最も重要な基礎です。胸式呼吸では息が浅く、声が安定しません。お腹を使って深く息を吸い、横隔膜の動きで支えることで、息の流れが安定し、喉に力を入れずに高音を出せるようになります。
練習の際は、仰向けになって腹部が上下するのを感じながら呼吸すると、腹式の感覚をつかみやすくなります。息の支えができると、5トーンスケールで音を上下させても音程が崩れず、5オクターブを目指すための土台がしっかり整います。
リップロールで喉の力みを解消する
リップロール(唇を震わせる発声)は、喉の緊張をほぐし、自然な息の流れをつくる練習法です。声を出す前にリップロールを行うことで、息と声が一体化し、喉を締めずに発声する感覚が身につきます。5トーンスケールと組み合わせると、音程の移動をスムーズに行う練習にもなります。
特に高音練習の前に行うと、声帯を温めながら無理のないフォームで練習でき、結果としてオクターブの幅を自然に広げることができます。
リップロールについては下記でも詳しく解説しています。5オクターブを目指している方は是非ご覧下さい。
共鳴ポイントを意識して声を響かせる
5オクターブに到達するためには、声を「力」で出すのではなく、「響き」で支える意識が必要です。
声を頭の中や鼻腔に響かせることで、高音が通りやすくなり、喉への負担も軽減されます。共鳴ポイントを探すには、軽くハミングをして頭の中に振動を感じる練習が効果的です。この感覚を保ったまま5トーンスケールを行うと、音が自然に上に抜けていき、オクターブの上限を押し広げることができます。
姿勢とフォームを整えて声の通り道を作る
正しい姿勢も、5オクターブを出すうえで欠かせません。
背筋をまっすぐに伸ばし、肩や首の力を抜くことで、声がスムーズに前へと通ります。猫背や前傾姿勢になると、呼吸が浅くなり、声の響きがこもってしまいます。立って発声する際は、足を肩幅に開き、体の軸をまっすぐ保つことを意識しましょう。
姿勢が整うと、息の流れと共鳴が自然に連動し、5トーンスケールで音を移動する際にも無理なくオクターブを超えていけるようになります。
5 オクターブ級の音域を持つ歌手たち(憧れの声域を知るために)
「5 オクターブ」という目標をより身近に感じてもらうため、実際にその音域(またはそれに近い)を持つ歌手を数名紹介します。自分の声域を広げたいと考えているなら、こうした先達の声の使い方から学べるヒントがあります。
Mariah Carey
Mariah Carey は「5 オクターブの声域を持つ」と言われており、地声からホイッスル・レジスターまで自在に操ることで有名です。
彼女の声は「低域は深くアルト寄り、そこから高域まで滑らかに繋がる」と評され、女性に限らず高音が出にくいと感じている方にとっては、発声の幅=可能性の象徴とも言えます。
5 オクターブを完全に自由に使えている人は稀ですが、彼女のような声の使い方を見ることで「この領域も理論上、近づけるものだ」という感覚を掴むことができます。
Minnie Riperton
Minnie Riperton は1970年代に活躍したソウル/ポップシンガーで、彼女も「5 オクターブの音域」を持つ歌手として名を馳せています。
代表曲「Lovin’ You」では非常に高い声(ホイッスル領域)を用いており、高音が出ないと悩む声質の方にとって「裏声・ホイッスルを鍛える」という方向性を示してくれるモデルです。彼女の声の特長=声帯の柔軟性と、息の支えを意識した発声が、高音域を拡げるための鍵になっていることが分かります。
Morten Harket
Morten Harketはバンド A‑ha のボーカルとして知られるノルウェーの歌手です。ポップ・ロック系でこのような広い音域を持つ例としても興味深く、男女問わず音域を広げ
たい5オクターブを目指したいという方にとって、ジャンルを超えたロールモデルになります。
5オクターブの声を目指すために知っておきたい注意点
5オクターブの音域を目指すことは、決して不可能ではありません。
ただし、間違った方法で高音を追いかけると喉を痛めたり、声帯に負担をかけてしまうこともあります。安全に、そして効率的に音域を広げていくためには、正しい知識と練習ペースを守ることが大切です。ここでは、5トーンスケールを使って5オクターブに近づく際に気をつけたいポイントを解説します。
無理な発声を避けて喉を守る
高音を出したい一心で、力任せに声を出すのは禁物です。喉を締めて無理に出すと、声帯に炎症やポリープができる原因になります。5オクターブを目指す場合は、喉に余分な力を入れず、息の流れを感じながら「軽く当てる」感覚で発声することが重要です。
高音が苦しいと感じたら一度休み、低い音域から再スタートする勇気も必要です。声は筋肉と同じで、急に無理をさせると壊れてしまうため、焦らず丁寧に鍛えることが成功への近道です。
練習量よりもフォームを重視する
5オクターブの音域を得るには、長時間の練習よりも「質の高い発声フォーム」を優先すべきです。
どれだけ練習を重ねても、喉に力が入っていたり、息が止まっていたりすると上達は難しくなります。1日10分でも構わないので、正しい姿勢・呼吸・喉の開きを意識して練習しましょう。
特に5トーンスケールは音の移動が細かいため、わずかな力みや息の乱れも影響します。短時間でも集中して行うことで、確実にオクターブの幅を広げることができます。
体調や喉のコンディションを確認する
声帯は非常に繊細な器官で、体調の影響を受けやすいものです。風邪気味の日や睡眠不足、乾燥した環境では高音が出にくくなることがあります。
女性の場合、ホルモンバランスの変化によっても声帯がむくみやすくなるため、無理に高音を出そうとするのは避けましょう。体がリラックスしている状態でこそ、正しいフォームが保てます。発声練習の前に軽くストレッチを行い、喉を温めてから5トーンスケールに取り組むことをおすすめします。
喉のケアについては下記でより詳しく解説していますので是非ご覧ください。
定期的なボイストレーニングで限界を更新する
自己流で練習を続けると、間違ったクセがついて音域の伸びが止まることがあります。
専門のボイストレーナーに定期的にチェックしてもらうことで、自分では気づけないフォームのズレを修正できます。特に5オクターブのような広い音域を目指す場合、細かい発声のコントロールが必要です。
NAYUTASでは、声帯の特性に合わせた個別指導を行い、あなたの限界を安全に少しずつ広げていくことが可能です。
ボイトレの基礎5トーンスケールに関する質問
5トーンスケールは、音楽の基礎力を高めるだけでなく、音域の拡大や声の安定にも役立つ練習法です。
ここでは、ボイトレ初心者から上級者までよく寄せられる質問をまとめました。練習を始める前に知っておくことで、より効果的にスキルアップを目指せます。
Q1:5トーンスケールとはどんな練習ですか?
A:5トーンスケールは、5音だけを上昇・下降させながら発声するボイストレーニングの基本練習です。音階の動きを滑らかに行うことで、声帯の柔軟性やピッチ感が自然に鍛えられます。初心者でも取り組みやすく、発声フォームの確認にも最適な練習です。
Q2:どれくらい練習すれば効果が出ますか?
A:個人差はありますが、毎日5〜10分でも継続すれば効果が現れます。最初は音が不安定でも、1〜2週間ほどで喉の動きが軽くなり、音のつながりがスムーズになる人が多いです。焦らず、少しずつ正しいフォームを身につけることが大切です。
Q3:5トーンスケールで5オクターブ出せるようになりますか?
A:5トーンスケールを続けることで音域を広げることは可能ですが、いきなり5オクターブを出せるようになるわけではありません。トレーニングの目的は「声帯の柔軟性を高め、地声と裏声を滑らかに繋げること」です。結果として3〜4オクターブ以上をカバーできるようになり、プロの歌手のような広い音域に近づいていくことが期待できます。
Q4:高音が苦手なのですが、どんな練習をすればいいですか?
A:高音を出すときは、喉に力を入れず「息の流れ」で支えることが重要です。リップロールやハミングなど、喉をリラックスさせる練習から始めましょう。5トーンスケールを使って地声から裏声へ少しずつ音をつなぐことで、喉を痛めずに高音を出せるようになります。
Q5:ボイトレに通うとき、どんな点を意識すれば上達しますか?
A:レッスンでは、ただ声を出すだけでなく「姿勢」「呼吸」「共鳴」の3つを常に意識しましょう。自分では気づきにくい癖も、プロの指導で修正できます。NAYUTASでは、一人ひとりの声のタイプに合わせたカリキュラムで、効率的に音域を広げるサポートを行っています。
【まとめ】
ボイトレの基礎5トーンスケールで音楽力をレベルアップさせよう!

ボイトレの5トーンスケール練習についてまとめました。
発声練習といえばコレ!といえるほど、おなじみの練習ではありますが、しっかり練習してテクニックを身につけようとすると、簡単なことではなく、奥も深いです。
そして、スケールはすべての音楽(音楽理論)の基本です。
スケール練習を繰り返し行えば、音楽的な力も身につき、歌唱にも役立ってきます。
効果が出るまでは時間がかかるかもしれませんが、諦めずに、少しずつでよいのでコツコツ進めていきましょう。