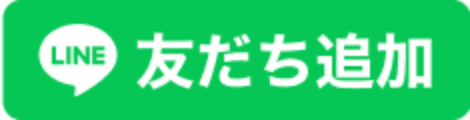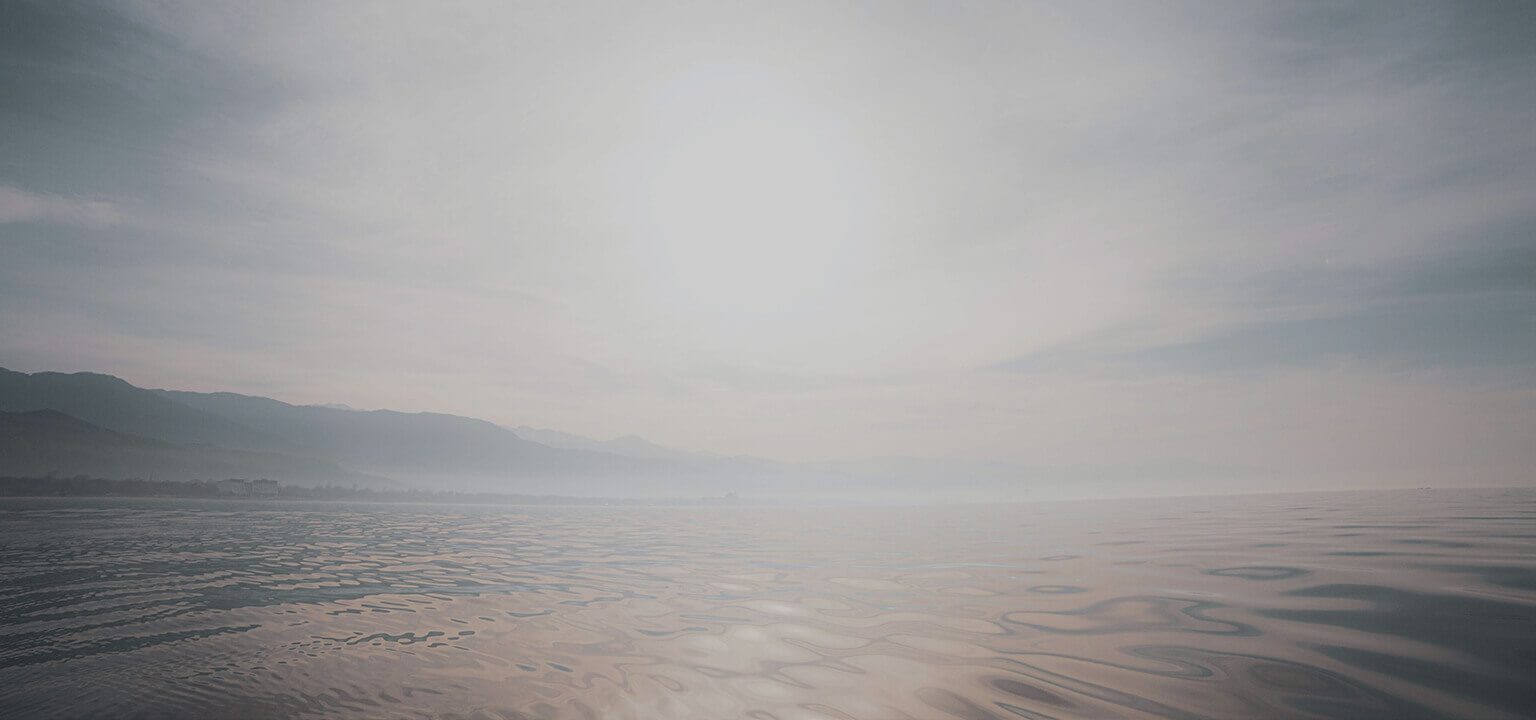「歌は話すように」「感情を込めて」「もっと自然に」
ボイストレーニングや音楽の現場で、よく聞くアドバイスです。
でも、よく考えてみてください。
人は本当に“話すように”歌っているのでしょうか?
そして、感情を込めればうまく歌えるのでしょうか?
今回は、一般的に信じられている“歌の常識”にあえて疑問を投げかけながら、歌と感情の意外な関係性を探ってみたいと思います。
■「話すように歌う」は本当か?
「話すように歌って」と言われたことのある人は多いはずです。
でも、実際にやってみると――難しい。
それもそのはず。話す声と歌う声は、使っている筋肉も、声帯の使い方も、呼吸の仕方も全く違うのです。
例えば、日常会話で使っている声帯は、ごく自然に、力を抜いて振動させています。でも、歌声では、ピッチ(音程)をコントロールしながら、より長く、強く、安定した振動を保つ必要があります。これは“別の楽器”と言ってもいいくらいの違いです。
つまり、「話すように歌う」とは、「話し声の自然さや感情の流れを、歌声に応用してみてね」という比喩的なアドバイスに過ぎないのです。
誤解して“話し声そのまま”で歌おうとすると、逆に不自然になったり、声が出しづらくなったりします。
■「感情を込めて」は時に逆効果?
感情を込めることは、もちろん大切です。
でも、ここに落とし穴があります。
初心者が「感情を込めよう」とすると、つい力んでしまう。
表情が硬くなり、声が震え、ピッチも不安定に――。
まさに「気持ちはあるけど伝わらない」状態です。
実は、本当に感情を伝えられるのは、歌の技術がある程度安定してから。
筋肉のコントロールができて、呼吸や共鳴が整って初めて、感情が「音」として聴き手に届くようになるのです。
つまり、感情は「込める」ものというより、「自然に湧き上がるものを、技術で支える」もの。
プロの歌手たちが感動を与えるのは、感情と技術が一致しているからなのです。
■歌うことは“脳と身体の再統合”?
少し変わった視点で見ると、歌うという行為は「脳と身体をつなぐ作業」とも言えます。
私たちの脳は、「こう歌いたい」「こう響かせたい」とイメージします。
でも、その通りに身体が動いてくれるとは限りません。
喉が詰まる、息が続かない、高音で裏返る…。
これは、脳が出す“命令”と身体の“反応”がずれている状態です。
歌のトレーニングとは、このズレを少しずつ減らしていく作業。
まるで、脳と身体の対話を取り戻すようなプロセスです。
実際、歌の上達によって「自分の気持ちが以前より言葉にできるようになった」と話す生徒さんもいます。
歌うことは、自分自身と向き合う行為でもあるのです。
■「音痴」は才能ではなく“身体の錯覚”?
音程が取れない、リズムに乗れない…
いわゆる“音痴”と呼ばれる悩みも、実は身体感覚のズレに原因があります。
例えば、声が出ているつもりでも、実際には違う音程だったり、リズムが微妙にズレていたり。
これは「耳」「声」「身体の感覚」が一致していない状態です。
つまり、音痴は“感覚のチューニング不足”によるもので、練習次第で直せるのです。
事実、音痴矯正に成功して、今ではライブ活動をしている人も少なくありません。
■体験レッスンで見える“新しい自分”
歌は、単なる趣味ではありません。
身体と心をチューニングし直し、自分自身を深く知る手段でもあります。
・もっと声を出したい
・感情を伝えられるようになりたい
・音痴を直したい
・人前で堂々と歌いたい
そう思ったことがある方は、一度「体験レッスン」に参加してみませんか?
ほんの30分〜60分のレッスンでも、「こんな声が出るんだ」「自分って意外と歌えるかも」といった驚きがあるはずです。
あなたの中に眠っている“本当の声”に、出会ってみましょう。
まずは体験から、一歩踏み出してみてください。
【体験レッスンはこちらから】