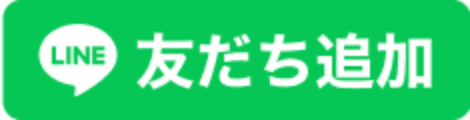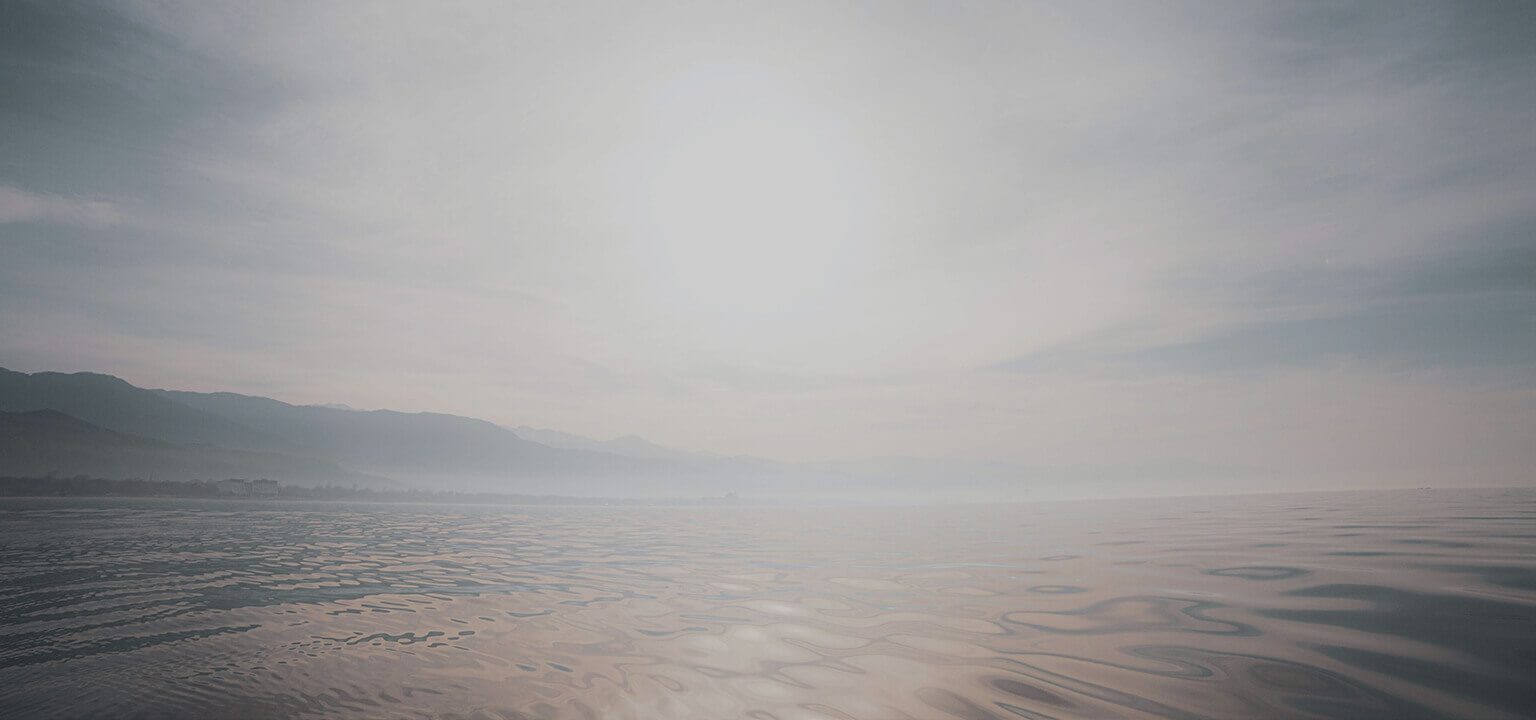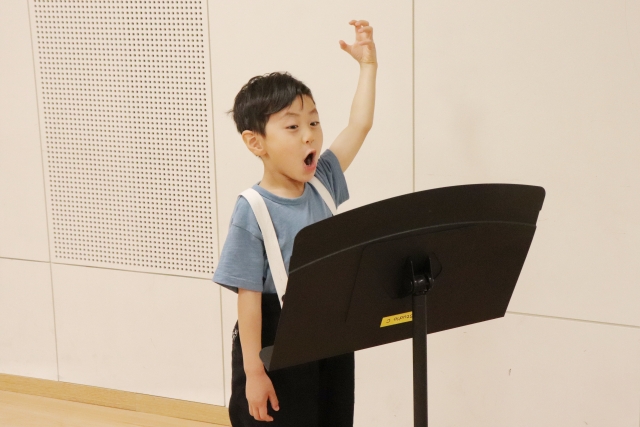歌やボイトレを続けていると必ず出てくるテーマが「鼻腔共鳴」。
高音をラクに出したい、声を細くしたくない、まっすぐ響く声を手に入れたい──そんなときに鼻腔の響きは欠かせません。
ところが、実際に鼻腔に響かせようと頑張るほど、
-
こもった鼻声になる
-
くぐもった音色になる
-
自分でも「変な響き」だとわかる
-
原因は分からないけど不自然な声になる
こんな悩みにぶつかる人がとても多いです。
今回は、「鼻腔に響かせたいのに鼻声になってしまう原因」と、その対処法をわかりやすく解説していきます。
「鼻腔共鳴」はコツさえつかめば誰でも身につけられるスキルなので、ぜひ参考にしてみてください!
◆ 鼻腔に響かせる=鼻声ではない
まず大前提として、
鼻腔共鳴と鼻声はまったく別物です。
鼻腔共鳴は、鼻の奥にある空洞(鼻腔)に声の響きを軽く通すことで、声が明るく伸びやかになるテクニック。
一方で鼻声は、鼻の穴の手前で空気が詰まったり、軟口蓋(上あごの奥)が下がっていたりして、声が鼻側に「逃げている」状態です。
つまり、
-
響きが前に通っている=鼻腔共鳴
-
鼻の手前で止まってしまう=鼻声
この違いを理解するだけでも、改善が早くなります。
◆ 鼻声になる主な原因3つ
① 「鼻に響かせよう」と意識しすぎている
多くの人が、鼻腔共鳴のイメージを“鼻に声を入れる”と勘違いしています。
実際は、鼻に声を入れようとするほど鼻声になります。
鼻腔はあくまで「声が勝手に通る場所」であって、「押し込む場所」ではありません。
② 軟口蓋(のどちんこの奥)が下がっている
軟口蓋が下がっていると、鼻腔と口腔の仕切りが弱まり、空気が鼻側に漏れてしまいます。
これが典型的な鼻声の原因。
軟口蓋は、
-
あくびのイメージ
-
口を“奥に”開ける感覚
を使うと上がりやすくなります。
③ 喉の力が抜けず、響きのスペースが狭い
喉が詰まっている状態だと、声が口にも鼻にもスムーズに抜けません。
結果、出口を探して鼻方向に逃げてしまい、鼻声になります。
喉の余計な力を取るためには、エッジボイスやリップロールなど「脱力系のエクササイズ」が効果的です。
◆ 鼻声を防ぎつつ、鼻腔に響かせるための実践トレーニング
① ハミングではなく“ンー”のオープンハミング
普通のハミングは鼻声になりやすい人には難しいことも。
おすすめは 軽く口を開けたハミング(ンー)」。
-
口をうっすら開ける
-
「ンー」と言いながら鼻の奥に少しだけ通す
-
ほっぺあたりに響きが拡散する感覚を探す
鼻が詰まる感じがある場合は、軟口蓋が下がっているサインです。
② “ア”で鼻腔を感じる練習
鼻腔共鳴は母音“A”で掴むと早いです。
-
あくびの直前のように喉の奥をふわっと開ける
-
「アー」と軽く声を出す
-
声が顔の中心にスーッと抜けるイメージを持つ
ポイントは「鼻に入れる」ではなく、「勝手に前に抜ける」感覚を探すこと。
③ リップロールで喉の余計な力を抜く
鼻声の原因の多くは“喉の詰まり”なので、まず脱力するのが近道。
軽く唇を閉じて「ブルルルル」と出すだけで、
・喉の脱力
・息の流れ
・響きの方向
が整い、鼻腔共鳴の準備ができます。
④ 実は歌の表現でも鼻腔の響きは武器になる
鼻腔共鳴はただ発声をラクにするだけではありません。
歌のニュアンス作りにも大活躍します。
-
明るい声質を作れる
-
感情表現を立体的にできる
-
バラードで抜けのある細い声を作れる
-
高音で苦しそうに聞こえなくなる
つまり、鼻腔共鳴は“歌がうまい人の共通点”とも言えるほど大切な要素。
正しく使えると、あなたの歌の魅力は一気に引き上がります。
◆ 一人でやるより、プロと一緒が圧倒的に早い
鼻腔共鳴は、感覚的な部分が多く、
自分ひとりでは正しくできているか判断しにくい発声です。
-
鼻声と鼻腔共鳴の違いが分からない
-
正しい響きの位置がイメージできない
-
喉が詰まっているかどうか自分では判断できない
こんな悩みがあるなら、プロのボイストレーナーにチェックしてもらうだけで、上達スピードは劇的に上がります。
◆ まずは体験レッスンで「正しい響き」を体感してみませんか?
鼻腔共鳴ができるようになると、高音はラクになり、声が明るく抜け、歌の表現力まで大きく変わります。
「鼻声しかできない…」と感じている方こそ、改善の伸びしろが大きいタイミングです!
気になる方は、ぜひナユタスの体験レッスンで
正しい響き・正しい位置の感覚を一緒に掴んでみましょう。