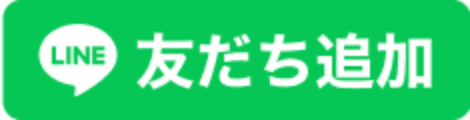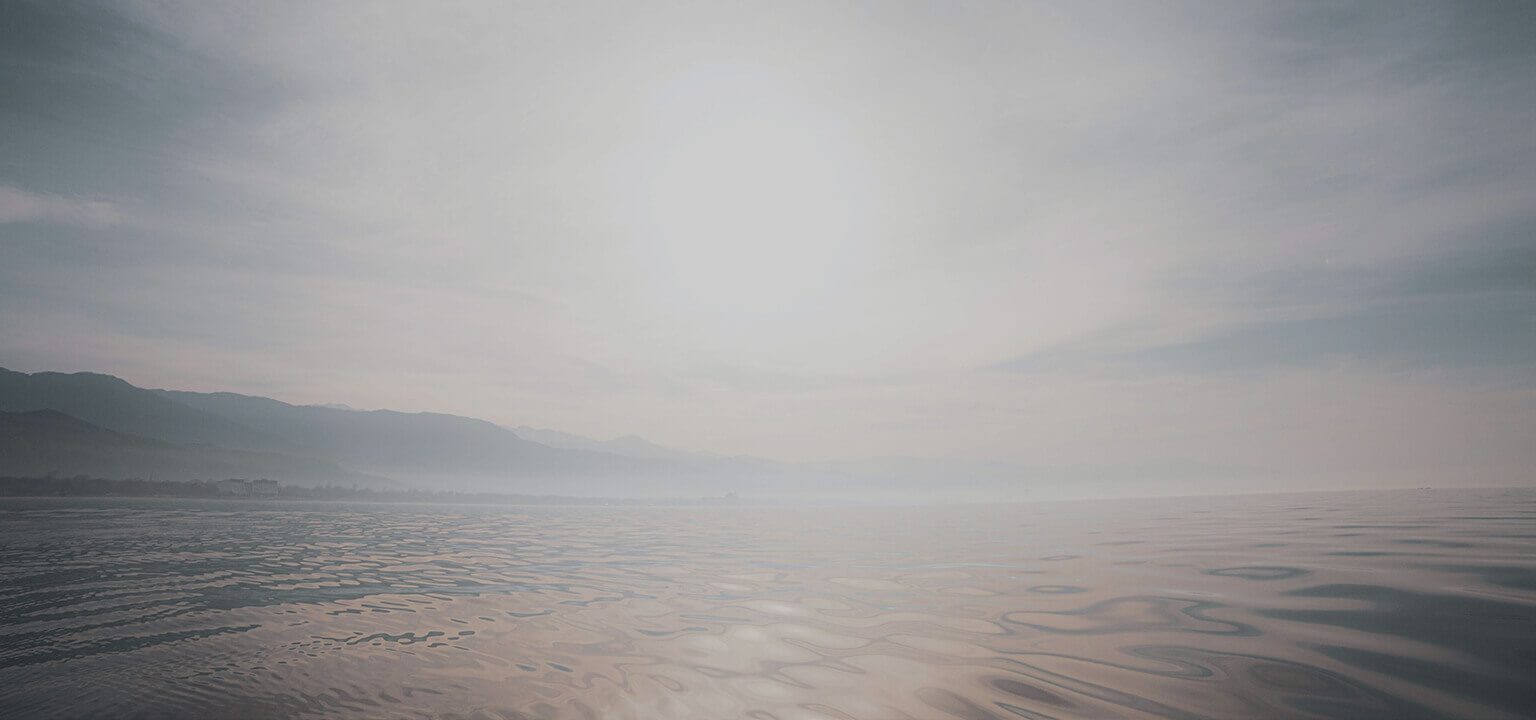1. 倍音とは?歌が上手い人の声に隠れた秘密 🎵
「なぜ、同じメロディを歌っても“上手い人の声”は響き方が違うのか?」
その理由の一つが、**倍音(ばいおん)**です。
倍音とは、声を出す際に生まれる**基本周波数(基音)**に対して、整数倍の周波数をもつ音成分のこと。
ひとつの声の中に複数の音が重なって響くことで、私たちは「厚み」「艶」「奥行き」を感じ取ります。
音響学的には、人の声は「基音」と「倍音」の組み合わせによって構成され、
これが“声の音色”を決定する重要な要素であるとされています。
たとえば、J-STAGEに掲載された猪本修氏の研究では、
成人の声に含まれる倍音成分を分析した結果、第3〜第6倍音が声質の違いに影響することが報告されています。
参照:「ヒトの声を題材とした音と音色の物理教材」https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsser/34/10/34_No_10_191002/_article/-char/ja/
(最終アクセス:2025年10月8日)
1.1 倍音の仕組みと人の声の違い
人の声は、**声帯の振動(音源)+声道の共鳴(フィルタ)**という二段構造で作られています。
このモデルは「ソース・フィルタ理論」と呼ばれ、声学の基礎理論として知られています。
声帯が振動して生まれる基音に対して、
口腔・鼻腔・咽頭といった共鳴空間が“フィルタ”の役割を果たし、
ある周波数帯を強調したり抑制したりして音色を作ります。
このとき、
共鳴が適切に行われるほど倍音が強調され、“通る声”や“響く声”が生まれます
逆に、喉を締めて力で出した声は倍音が失われ、
フラットでこもった印象になります。
筑波大学の研究(Yamamoto et al., 2013)でも、歌唱技法の解析において、
フォルマントの制御(共鳴)が倍音の出現に影響する
ことが確認されています。
参照:「A Computational Approach to Analysis and Detection of Singing Techniques」
https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/2013106/files/DA11313.pdf
(最終アクセス:2025年10月8日)
1.2 倍音が多い声=美しく響く理由
倍音が多い声が美しく聞こえるのは、聴覚心理学的な理由があります。
私たちの耳と脳は、
整数倍の周波数の重なりを「調和」として快く感じる
傾向があるためです。
つまり、倍音のバランスが整った声は、
自然と「豊か」「心地よい」「プロっぽい」と評価されやすいのです。
実際に、ドイツの音響学者F. Klingholzによる研究では、
オーバートーン唱法(倍音を強調して歌う技法)を分析し、
口腔の形状とフォルマント調整が倍音強調に直結することを示しました。
参照:「Overtone singing: productive mechanisms and acoustic data」
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8353624/
(最終アクセス:2025年10月8日)
また、Bloothooftらによる研究(オランダ・ユトレヒト大学)でも、
倍音の配置が聴覚上の“美しさ”に影響することが確認されています。
参照:「Acoustics and perception of overtone singing」
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1401528/
(最終アクセス:2025年10月8日)
🎤 まとめ
倍音は「特別な才能」ではなく、科学的に鍛えられる要素です。
声の響きを決めるのは力ではなく、共鳴のコントロール。
腹式呼吸・リラックスした喉・正しい姿勢を意識することで、
誰でも倍音の豊かな声に近づくことができます。
ボイストレーニングでは、こうした倍音と共鳴の関係を意識した発声を行うことで、
「声が通らない」「こもる」といった悩みを根本から改善できます。
科学的根拠に基づく練習で、あなたの声は確実に変わります。✨
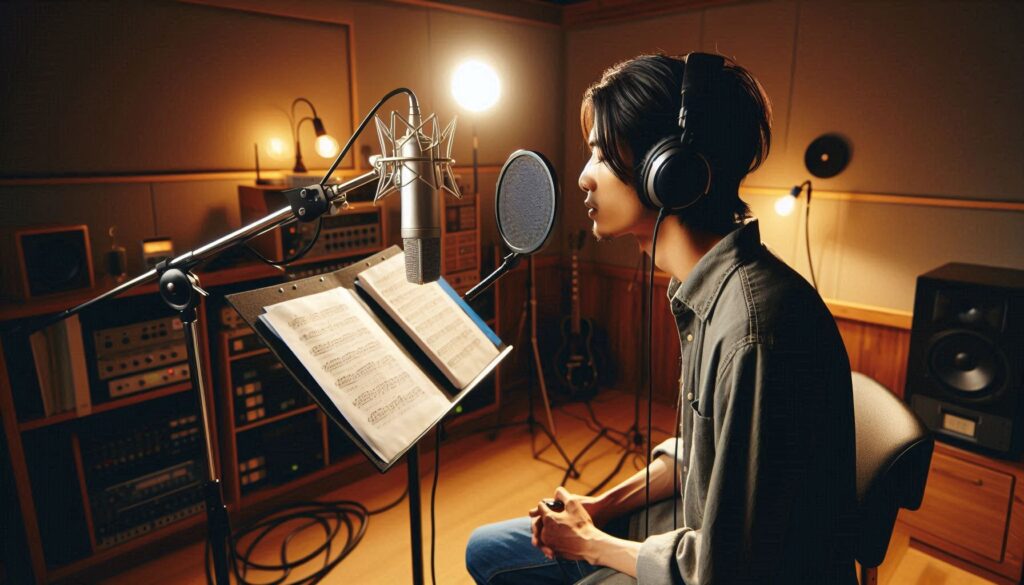
2. ボイトレで倍音を増やすメリット 🎶
「倍音を意識した発声を続けると、どんな変化があるの?」
実は、倍音を増やすボイトレは“響きの強化”だけでなく、声の印象・持続性・聴き取りやすさに直結します。これは感覚的な話ではなく、音響工学や発声生理学によって裏付けられた事実です。
2.1 声の厚みと艶が増す理由
倍音が豊かになると、声のスペクトル(音の分布)が広がり、同じ音量でも「厚み」や「存在感」が生まれます。
この現象は「歌い手のフォルマント(Singer’s Formant)」と呼ばれ、
3kHz付近の倍音帯域が強調されることで、人の耳に通る声
が形成されます。
J-STAGEに掲載された猪本修氏の論文(2020年)によれば、成人男女116名の声を解析した結果、
第3〜第6倍音が音色と聴覚印象に強く関与することが示されています。
参照:「ヒトの声を題材とした音と音色の物理教材」
👉 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsser/34/10/34_No_10_191002/_article/-char/ja/
(最終アクセス:2025年10月8日)
さらに、**国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)**による報告では、
声の厚みや明瞭度を決定するのは「声道の形とフォルマント構造」であるとされています。
特に、声道を広げることで第2フォルマント(F2)と第3フォルマント(F3)が接近し、
倍音が自然に強調されるメカニズムが確認されています。
参照:「高速ホルマント周波数抽出法と合成音によるその評価」
👉 https://www.nict.go.jp/publication/kiho/15/080/Kiho_Vol15_No080_pp495-506.pdf
(最終アクセス:2025年10月8日)
このように、倍音を増やすトレーニングは「喉の力を抜いて、響きを前方に導く」ことで、
結果的に声の“艶と奥行き”を生むことがわかります。
2.2 聴き取りやすく、疲れにくい声になる
倍音が整うと、声の**情報量(音素識別)**が増え、
少ない力で「届く声」「疲れにくい声」を実現できます。
筑波大学の研究(Yamamoto et al., 2013)では、
発声技術を解析した結果、
フォルマント制御が倍音の安定性と聴覚的明瞭度に寄与する
と報告されています。
参照:「A Computational Approach to Analysis and Detection of Singing Techniques」
👉 https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/2013106/files/DA11313.pdf
(最終アクセス:2025年10月8日)
また、NICTの研究報告によると、
声道の共鳴(フォルマント)と反共鳴(アンチレゾナンス)の最適化によって、
喉の疲労を抑えつつ声の明瞭度を高めることが可能であるとされています。
参照:「声道の形からのホルマント周波数の計算」
👉 https://www.nict.go.jp/publication/kiho/10/046/Kiho_Vol10_No046_pp016-026.pdf
(最終アクセス:2025年10月8日)
つまり、
倍音を意識した発声は“パワーで押す声”ではなく、
少ない力で遠くまで届く声を作るための、最も効率的な方法なのです
2.3 マイク乗り・伝達性が格段に上がる
倍音構造が整うと、音響機器でも声がクリアに録音・再生されます。
これは、倍音が「マイクの感度帯域(約2〜4kHz)」と重なるためです。
J-STAGEに掲載された「プロ歌手と学生における歌い手のフォルマント比較」では、
プロの歌手の声には3kHz帯域に安定した倍音ピークがあり、
機器を通しても音像が前に出やすいことが報告されています。
参照:https://www.jstage.jst.go.jp/article/asjsc/1/1/1_SC-2021-14/_pdf/-char/en
(最終アクセス:2025年10月8日)
🎤 まとめ
倍音を増やすボイトレは、科学的に見ても「声の効率化」と「音色改善」の両面に有効です。
-
声の厚みと艶が増す(フォルマント構造の最適化)
-
聴き取りやすく疲れにくい(息と共鳴の効率化)
-
マイクや録音環境で際立つ(倍音帯域の整合)
NAYUTAS宇都宮校では、倍音を最大限に引き出すマンツーマン指導を実施しています。
科学的なアプローチで「響きのある声」を育てる。
それが、あなたの声を“プロ仕様”へ変える第一歩です。✨

3. 倍音を引き出すボイトレ練習法5選 🎤
倍音を豊かにするには、単に「声を強く出す」ことではなく、
共鳴を操るトレーニングが必要です
ここでは、声帯・声道・息のバランスを整えながら、倍音を引き出すための実践法を5つ紹介します。
すべて科学的な裏づけがあり、初心者から上級者まで実践可能です。
3.1 ハミングで共鳴感を育てる
ハミング(鼻に響かせる発声)は、倍音を感じる最初のステップです
口を閉じ「んー」と軽く声を出すことで、口腔よりも鼻腔・上咽頭に音が共鳴し、
倍音の“響きの通り道”を体感できます。
この方法は、オーバートーン(倍音唱法)研究でも基礎となる共鳴法として知られています。
オランダの音響学者G. Bloothooftらは、倍音唱法を分析した論文
「Acoustics and perception of overtone singing」で、
倍音を明瞭に響かせるには複数のフォルマント(共鳴帯域)を調整する必要があると示しています。
参照:https://pubs.aip.org/asa/jasa/article-pdf/92/4/1827/11463901/1827_1_online.pdf
(最終アクセス:2025年10月8日)
ハミングで得られる“鼻腔の響き”は、このフォルマント操作の第一歩。
強く出そうとせず、脱力と息の流れを意識するのがコツです。
3.2 母音フォーム切り替えトレーニング(ア・オ・ウ)
母音を変えるだけでも倍音は劇的に変化します。
「ア→オ→ウ→イ→エ」とゆっくり切り替えながら発声すると、
口腔内の形が変化し、フォルマント位置(共鳴帯域)も移動します
声楽研究の第一人者 Johan Sundberg の論文
「Formant Tuning Strategies in Professional Male Opera Singers」では、
プロ歌手は音高に合わせてフォルマントを調整し、倍音を強調していることが明らかになっています。
参照:https://www.jvoice.org/article/S0892-1997%2812%2900209-3/abstract
(最終アクセス:2025年10月8日)
また、“Formant frequency tuning in singing”という研究では、
母音によって倍音が異なる強さで現れることが確認され、
特に「オ」「ウ」の母音で高次倍音が豊かに出やすい傾向が示されています。
参照:https://www.researchgate.net/publication/257293092_Formant_frequency_tuning_in_singing
(最終アクセス:2025年10月8日)
3.3 ロングトーンで倍音を安定させる
一音を10秒以上、息を一定に保ちながら伸ばす「ロングトーン」練習は、倍音を“定常的に維持する力”を鍛えます
特に「ア」や「オ」で行うと、フォルマントが安定しやすく、
倍音スペクトル(周波数分布)も滑らかに整います。
この練習は地味ですが、倍音構造を「固定」するには最適なんですよ
音の揺れを録音して聴き返すと、上達が明確にわかります
3.4 共鳴空間操作(舌・喉頭・軟口蓋の微調整)
共鳴空間を調整することで、倍音のピークを自在に動かせます。
舌を低く保ち、軟口蓋を軽く上げ、喉頭をリラックスさせると、
声道が広がり高次倍音が強調されます。
Wang(1986年)の研究「Singer’s High Formant and Voice Quality」では、
喉頭位置の変化と倍音強調の関係が明確に示されています。
参照:https://www.jstage.jst.go.jp/article/ast1980/7/6/7_6_303/_pdf
(最終アクセス:2025年10月8日)
また、その他の研究でも、
喉頭を下げ、咽頭を広げることで3kHz帯域のエネルギーが集中しやすくなることが報告されています。
この調整こそが「通る声」「厚い声」を生み出す要因なのです
3.5 弱音(ソフト発声)で響きを研ぎ澄ます
意外かもしれませんが、弱い声で発声すると倍音が明瞭になります。
小さな声では喉に余計な力が入らず、声道の共鳴をより繊細に感じ取れるからです。
“Formant frequency tuning in singing”の報告では、
低出力(soft voice)時にフォルマント変動が最小となり、
共鳴安定性が高まることが示されています。
参照:https://www.researchgate.net/publication/257293092_Formant_frequency_tuning_in_singing
(最終アクセス:2025年10月8日)
まずは1日5分、鏡の前で声の自分自身の弱音(ソフト発声)を観察してみましょう。
響きが顔の中央から額に上がるように感じられたら、倍音が育っている証拠です。✨
🎤 まとめ
倍音を引き出すボイトレは、
1️⃣ ハミングで共鳴感を掴み、
2️⃣ 母音でフォルマントを操作し、
3️⃣ ロングトーンで安定化し、
4️⃣ 共鳴空間を整え、
5️⃣ 弱音で精度を磨く
これらを組み合わせることで、
声は科学的にも“美しく・疲れず・通る”音へ変化します。
NAYUTAS宇都宮校では、マンツーマン発声分析を行い、
倍音が豊かに響く「プロ仕様の声」を育てています

4. 倍音を高めるための注意点とよくある勘違い ⚠️
倍音を増やそうとするあまり、誤った発声法で喉を痛める人が少なくありません。
「強く出せば響く」「高音を出せば倍音が増える」というのは、実は大きな誤解です。
ここでは、科学的視点から見た“正しい倍音強化”の注意点を整理します。
4.1 強く出すほど響く、は間違い
多くの初心者が「声量=響き」と勘違いします。
しかし、倍音は力ではなく共鳴の整い方で決まります。
スウェーデン王立工科大学(KTH)のJohan Sundberg氏は、
「声量を上げてもフォルマント(共鳴帯域)の構造が変わらない限り、倍音は増えない」
と述べています。
参照:「Formant Tuning Strategies in Professional Male Opera Singers」
https://www.jvoice.org/article/S0892-1997%2812%2900209-3/abstract
(最終アクセス:2025年10月8日)
同研究では、
声の響きは喉頭の位置と咽頭空間の広がりによって決まる
ことが明確にされています。
つまり、声を強く出すのではなく、**「声道をどう使うか」**が倍音を左右するのです。
4.2 高音=倍音が多い、ではない
「高い音を出すと倍音が増える」というのも誤解です。
確かに高音では周波数が上がり、倍音の数自体は増えますが、
それが“美しい響き”になるとは限りません。
京都大学の音声科学研究によると、
声の倍音構造と聴覚印象の関係は周波数よりもフォルマント分布に依存していると報告されています。
つまり、音高ではなく「どの帯域の倍音を強調するか」が重要です。
特に第2〜第4フォルマント(約1〜3kHz)を意識した練習が、
“通る声”や“艶のある声”を作る鍵になります。
4.3 喉に力を入れるほど倍音が減る
倍音が減る最大の原因は、喉の過緊張です。
喉に力が入ると声帯の振動が硬直し、倍音が失われます。
この現象は、国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)の報告でも確認されています。
参照:「声道の形からのホルマント周波数の計算」
https://www.nict.go.jp/publication/kiho/10/046/Kiho_Vol10_No046_pp016-026.pdf
(最終アクセス:2025年10月8日)
研究によると、喉頭を下げて咽頭を開くことで、
フォルマント帯域が安定し、**高次倍音(3kHz付近)**が強調されやすくなります。
つまり、
「喉を開く」意識が倍音を支える基本動作なのです
4.4 無理に“響かせよう”とすると逆効果
倍音を「作ろう」と意識しすぎると、
舌や顎に余計な緊張が入り、共鳴空間が狭まります。
特に「顔に響かせよう」とすると、上方向ばかりを意識して喉頭が上がりがちです。
この点について、東京大学大学院 工学系研究科の資料
「音響音声学レクチャー04(声道と共鳴)」では、
声道形状が変化するとフォルマントが乱れ、倍音ピークが不安定になることが示されています。
参照:https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/~mine/japanese/acoustics/lecture-04.pdf
(最終アクセス:2025年10月8日)
倍音は“響かせよう”ではなく、**“整えよう”**という姿勢で育てるのが正解です。
最も効果的なのは、
ハミングや母音切り替えなどの「自然な共鳴練習」
を継続すること
4.5 倍音は“音量”ではなく“設計”
倍音は筋力ではなく、音響設計の結果です。
つまり、息・姿勢・声道操作の3要素を整えることで自然に生まれるもの。
世界的な研究機関であるeLife誌掲載の論文
「Overtone focusing in biphonic Tuvan throat singing」では、
トゥバの伝統的な倍音唱法を分析し、
特定の周波数帯を選択的に強調することで倍音を焦点化できることを報告しています。
参照:https://elifesciences.org/articles/50476
(最終アクセス:2025年10月8日)
この研究は、倍音の美しさが「力」ではなく「制御」によって作られることを証明しています。
🎤 まとめ
倍音を増やすための正しい考え方は、以下の5点に集約されます。
-
声を強く出すより、共鳴空間を整える
-
高音に頼らず、フォルマント帯域を意識する
-
喉に力を入れず、脱力+息の流れを大切にする
-
「響かせる」ではなく「整える」発声
-
倍音は筋力ではなく、音響設計の成果
NAYUTAS宇都宮校のレッスンで倍音を育てて、声そのものが“楽器のように響く”感覚を体験してくださいね🎶
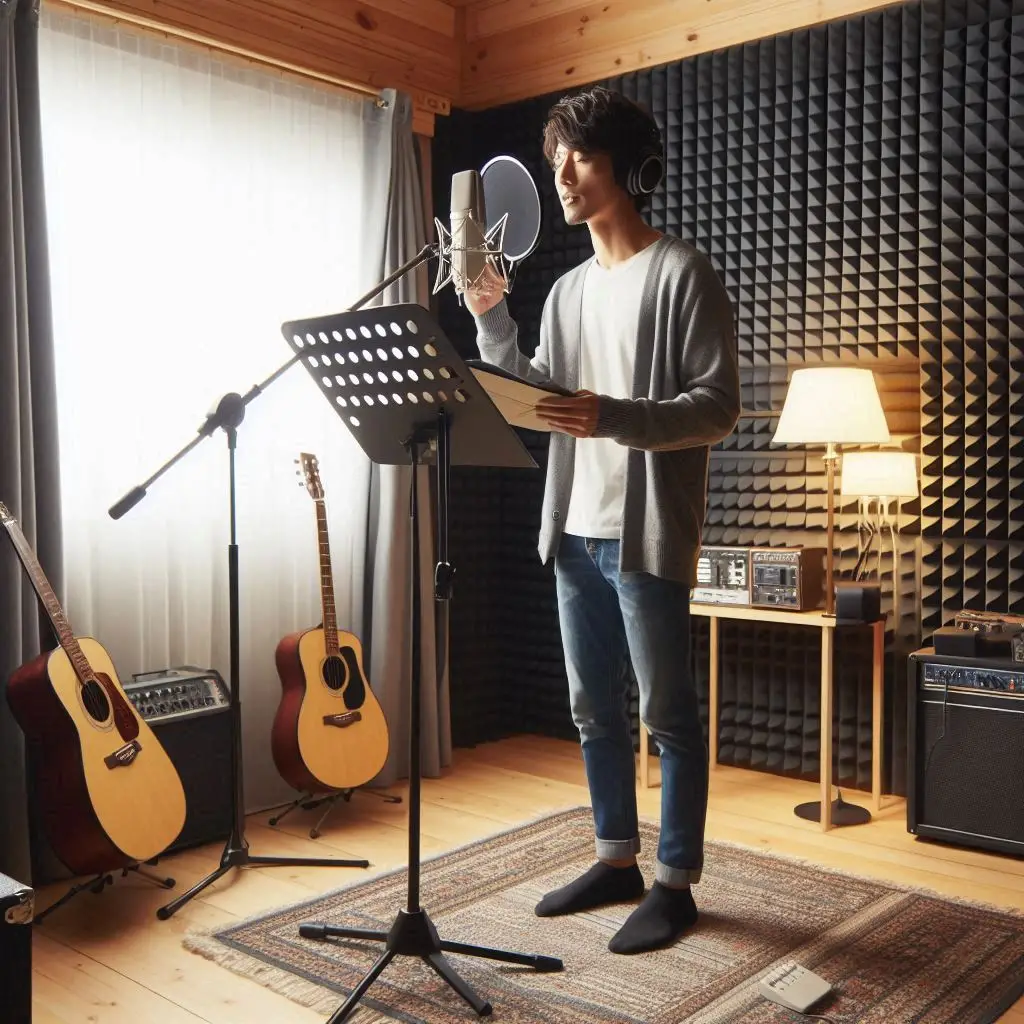
5. NAYUTAS宇都宮校で“響く声”を育てよう 🎶
ここまで見てきたように、倍音とは「感覚」ではなく音響学的に説明できる現象です。
声帯・声道・共鳴空間を正しく扱えば、誰の声にも“倍音の響き”は宿ります。
しかし、そのためには一人ひとりの声質や体の構造に合わせた緻密な発声分析が欠かせません。
それを可能にしているのが、NAYUTAS宇都宮校のボイストレーニングです。
5.1 科学的分析に基づくレッスン
NAYUTAS宇都宮校では、生徒の声が「どの帯域で響いているか」を客観的に評価し、最短で理想の声へ導きます。
倍音が出やすい姿勢・呼吸・母音フォームを調整していきます。
5.2 現役プロ講師によるマンツーマン指導
全レッスンは現役プロ講師による完全マンツーマン制で行われます。
講師陣は声優・シンガー・舞台俳優など多彩なバックグラウンドを持ち、声道操作・喉頭位置・息の圧力制御を丁寧に指導します。
そのため、「声がこもる」「高音がきつい」といった悩みを、
力任せではなく“響きの設計”で解決できます。
5.3 専用スタジオで“響く声”を体感する
校舎には防音スタジオとレコーディング設備を完備。
単に練習するだけでなく、自分の声を録音して倍音の変化を客観的に確認できます。
これは、音響学的に最も効果的な「聴覚フィードバック(auditory feedback)」学習です。
レッスンでは「自分の耳」だけでなく「波形・スペクトル・録音」を通して、
倍音がどのように変化しているかを可視化+体感できるのが特徴です。
5.4 初心者からプロ志望まで対応
NAYUTAS宇都宮校は、歌唱初心者から声優志望、
K-POP・J-POP・アニソンなどジャンルを問わず対応可能です。
倍音の扱い方はジャンルごとに異なりますが、
すべてに共通するのは「共鳴の理解が基礎にある」ということ。
倍音研究の分野でも、
eLife誌掲載の「Overtone focusing in biphonic Tuvan throat singing」
https://elifesciences.org/articles/50476
(最終アクセス:2025年10月8日)
は、倍音制御の汎用性を示しており、
ジャンルを超えた応用可能性があることを証明しています。
NAYUTASのレッスンでは、これらの理論を音楽ジャンルに合わせて最適化し、
一人ひとりの「個性ある響き」を引き出します。
🎤 まとめ
倍音の豊かさは、才能ではなく科学的アプローチと習慣の積み重ねで作られます。
NAYUTAS宇都宮校では、
-
最新の音響分析
-
科学理論に基づくマンツーマン指導
-
プロ講師による実践的アドバイス
-
録音による倍音フィードバック
を組み合わせ、あなたの声を「共鳴する楽器」へと育てます。
体験レッスンでは、わずか30分で“声の響き”が変わる瞬間を体感できます
📍体験申込はこちら → NAYUTAS宇都宮校 公式サイト
◆◇*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*◇◆
宇都宮でボイトレするならNAYUTAS宇都宮校!
JR宇都宮駅東口から徒歩4分のボイストレーニング教室
プロ講師によるマンツーマンレッスン
K-POP・洋楽・アニソン・話し方にも対応!
初心者からプロ志望までOK!
\ 【期間限定キャンペーン】開催中! /
今なら初回体験レッスン(通常6,600円)が無料!
さらに、体験後3日以内のご入会で入会金(通常11,000円)も無料!
(毎月先着10名限定)
【ボイストレーニング&ダンス NAYUTAS宇都宮校】
〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2丁目5−3 MYビル 1階
TEL.028-689-8166
アクセス抜群!
・JR宇都宮駅 東口 徒歩4分
・宇都宮LRTライトライン 東宿郷駅 徒歩1分
・宿郷町バス停前
「好きな曲を上手に歌いたい!」「音痴を克服したい!」「自分に合った発声法を学びたい!」
そんなあなたの夢を叶えるボイトレなら、NAYUTAS宇都宮校にお任せください
詳しくはこちら
無料体験レッスンを予約する
◆◇*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*◇◆