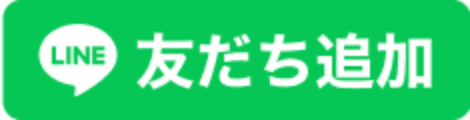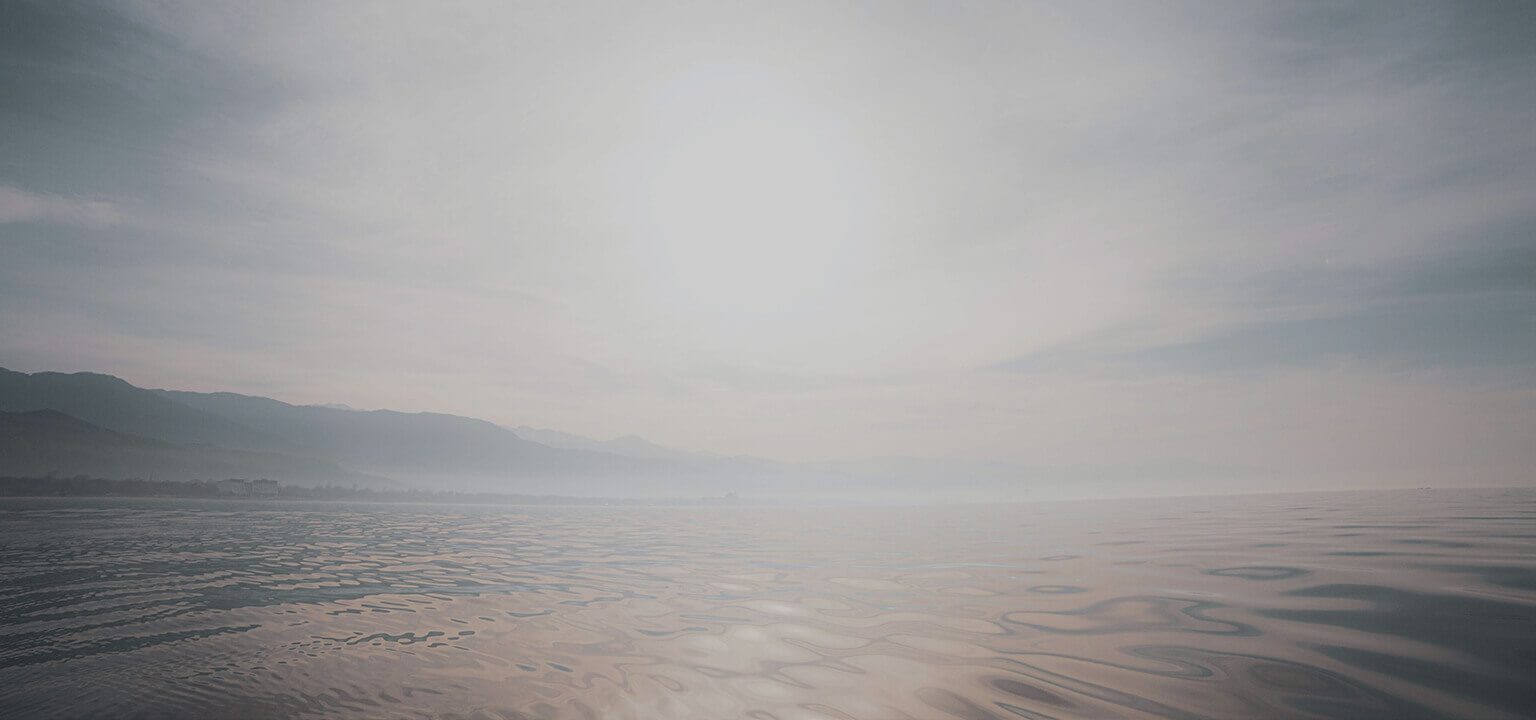楽器や歌の練習で「ロングトーンが大事」とよく言われますが、実際に続けてみると「息が続かない」「音が揺れる」「すぐ疲れる」といった悩みを感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし、ロングトーンはただの基礎練習ではありません。音楽の“根っこ”を育て、表現の幅を大きく広げてくれる大切なトレーニングです。今回は、ロングトーンを上達させるためのポイントを、具体的な方法と意識の持ち方からお伝えします。
1. 正しい姿勢と呼吸から始めよう
ロングトーンは「息のコントロール」がすべての鍵です。まず意識すべきは姿勢。背筋を無理に伸ばすのではなく、頭のてっぺんから糸で吊られているように、体をまっすぐに保ちます。肩や首の力を抜き、胸を開いて呼吸が自由に入る状態をつくりましょう。
呼吸は胸で浅く吸うのではなく、腹式呼吸を意識します。お腹や腰のまわりに空気をためるように深く吸い込み、吐くときはお腹を少しずつへこませながら、細く長く息を出します。この「息を押し出す力」が音の安定につながります。
2. 音を“まっすぐに保つ”意識を持つ
ロングトーンの練習では、「どれだけ長く伸ばせるか」よりも、「どれだけ同じ音質を保てるか」が重要です。最初の音と最後の音の音量・音程・響きができるだけ変わらないように意識しましょう。
練習のコツは、耳をよく使うこと。自分の音を録音して聞いてみると、思った以上に音が揺れていたり、最後が弱くなっていたりすることに気づきます。
鏡を見ながら口元や姿勢をチェックするのもおすすめです。少しの体の緊張や息のムラが、音の不安定さに直結していることが分かるはずです。
3. 無理をせず、少しずつ時間を延ばす
ロングトーンの練習でありがちな失敗が、「長く吹こう(歌おう)」と頑張りすぎて息が乱れ、体が力んでしまうことです。最初は5秒〜8秒程度からスタートし、慣れてきたら10秒、15秒と段階的に延ばしていきましょう。
疲れたと感じたらすぐに休むことも大切です。筋トレと同じで、無理に続けると逆効果。正しいフォームで少しずつ積み重ねることで、自然と持久力と音の安定感が身についていきます。
4. 音の「入り方」と「終わり方」を丁寧に
ロングトーンでは、音の出だしと終わり方を丁寧にコントロールできると、音楽的な表現力が一気に上がります。
出だしは「ふっ」と息を押し出すのではなく、息を“音に変える”感覚でスムーズに。終わりは急に切らず、少しずつ息を細めて音が自然に消えていくように意識しましょう。
この練習を続けると、フレーズの中での息の使い方やダイナミクス表現も格段に上達します。
5. ロングトーンは「音を育てる時間」
単調に感じやすいロングトーンですが、実は自分の音とじっくり向き合える貴重な時間です。
「今日はどんな音が出るかな?」「昨日より響きが豊かになったかな?」と、日々の変化を感じながら続けることで、自分の音に対する感覚がどんどん磨かれていきます。
音をまっすぐ育てる練習を続けるうちに、曲を演奏するときの安定感や表現の幅が大きく広がっていくはずです。
まとめ:ロングトーンの積み重ねが“音楽力”をつくる
ロングトーンは、一見地味な練習に思えるかもしれません。ですが、どんなにテクニックのある演奏家・歌手でも、ロングトーンを大切にしています。
「音をまっすぐに伸ばす」ことは、結局のところ“自分の音”を育てること。焦らず、丁寧に続けることで必ず結果が現れます。
もし「自分のロングトーンがうまくいかない」「もっと安定した音を出したい」と感じているなら、プロの視点で一度チェックしてもらうのもおすすめです。
当教室では、呼吸法や姿勢、音の出し方まで、一人ひとりの体に合わせたアドバイスを行っています。
NAYUTASの体験レッスンでは、あなたの音を実際に聴きながら、すぐに実践できる改善ポイントをお伝えします。
ぜひ一度、“自分の音を磨く時間”を体験してみてください。
体験レッスンはこちら