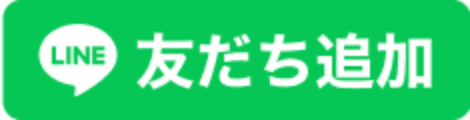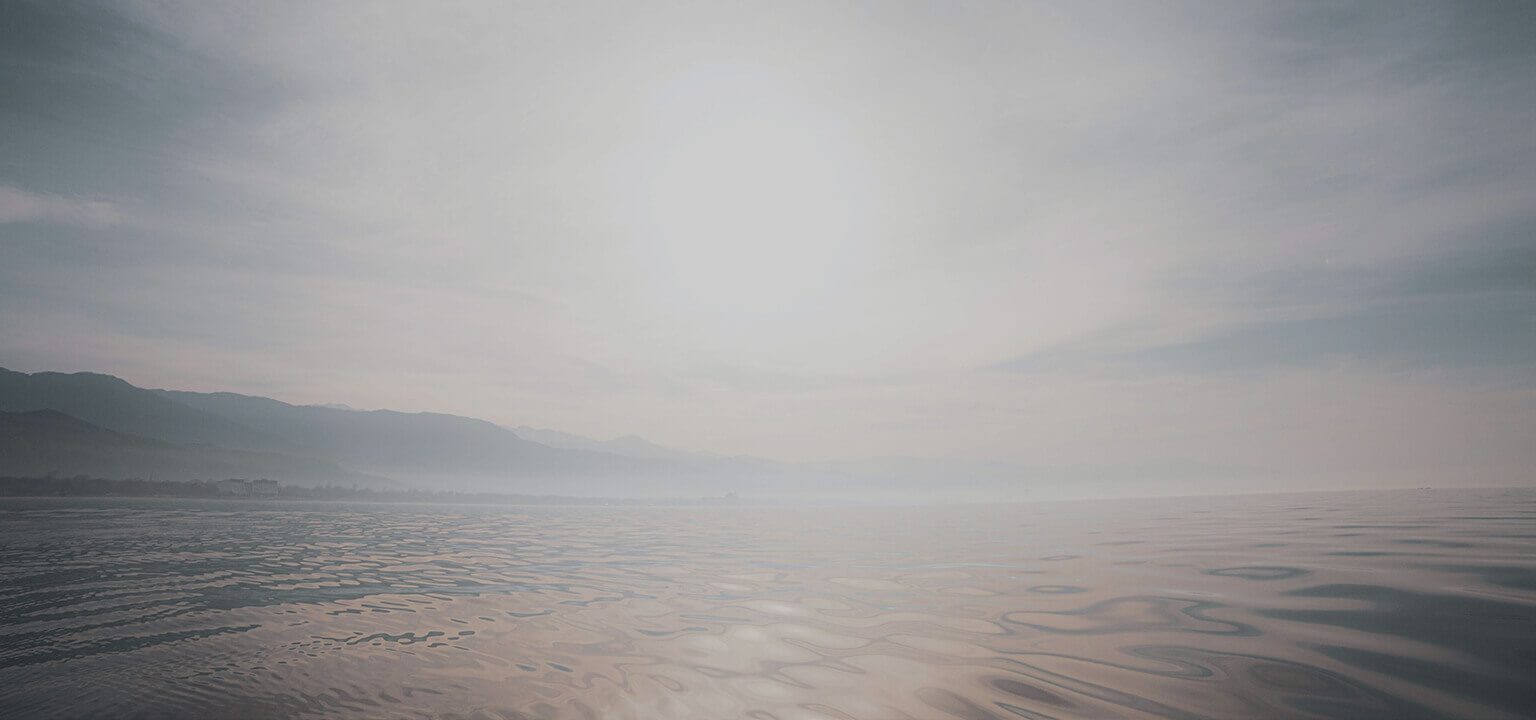こんにちは!NAYUTAS(ナユタス)町田校です。
ボイトレに関連する用語を「ボイトレ用語辞典 〜ナユタス町田校編〜」シリーズとして五十音順で網羅し、わかりやすく解説していきます。
第15回は、さ行⑤「そ」です。
【関連記事】
ボイトレ用語辞典 〜ナユタス町田校編〜 #14 さ行④「せ」
ボイトレ関連の「そ」から始まる用語
ボイトレ関連で「そ」から始まる、主な用語の一覧は、次のとおりです。
- そ【ソ】
- そああゔぇ【ソアーヴェ】
- そう【箏】
- そうしょくおん【装飾音】
- そうたいおんかん【相対音感】
- そうほう【奏法】
- そうるみゅうじっく【ソウルミュージック】
- そくどひょうご【速度標語】
- そすてぬうとぺだる【ソステヌート・ペダル】
- そなたけいしき【ソナタ形式】
- そふとぱれっと【ソフトパレット】
- そふとぶれす【ソフト・ブレス】
- そぷらの【ソプラノ】
- そり【ソリ】
- そりすと【ソリスト】
- そるふぇえじゅ【ソルフェージュ】
- そろ【ソロ】
- そろあるばむ【ソロ・アルバム】
- そん【ソン】
- そんぐらいてぃんぐ【ソングライティング】
- そんご【ソンゴ】
- そんはちょろ【ソン・ハロチョ】
そ【ソ】
音楽における「ソ」は、ドレミファソラシドの音階における第5音で、英語では「G」と表記されます。音階の中で重要な役割を果たし、和音の構成や旋律の進行において基盤となる音です。
ボイトレにおいては、「ソ」の音は中音域に位置し、発声練習や音程の確認に頻繁に使用されます。この音を安定して出せるようになれば、ほかの音域への移行もスムーズになるでしょう。
そああゔぇ【ソアーヴェ】
ソアーヴェ(soave)は、イタリア語で「柔らかく」「優しく」「甘美に」といった意味を持つ音楽用語です。楽譜上では、演奏者に対して柔らかく優美な表現を求める際に使用されます。
ボイトレにおいては、「ソアーヴェ」の指示がある場合、声を柔らかく滑らかにコントロールする技術が求められます。この表現力を身につけることで、歌唱の幅が広がり、聴衆に深い感動を与えることができます。
そう【箏】

箏(そう)は、日本の伝統的な弦楽器で、一般には「琴(こと)」とも呼ばれます。13本の弦を持ち、指や爪で弾いて演奏します。古くから日本の音楽文化に根付いており、雅楽や民謡などで使用されています。
ボイトレにおいては、箏の音色や旋律を学ぶことで、日本の伝統音楽のリズム感や音階感覚を養えます。これにより、和のテイストを取り入れた歌唱表現が可能となるでしょう。
そうしょくおん【装飾音】
主音を飾るために付加される短い音のことで、トリルやモルデント、グレースノートなどが含まれます。楽曲に華やかさや、表現の豊かさを加える役割を持つ音です。
ボイトレにおいては、装飾音の技術を習得することで、歌唱における表現力や技巧が向上します。これにより、より魅力的で感情豊かなパフォーマンスが可能となるでしょう。
そうたいおんかん【相対音感】
基準となる音と別の音を比較し、その音程差から音の高さを判断する能力です。これは「絶対音感」と対比される概念で、後天的な訓練によって習得可能とされています。
ボイトレにおいては、相対音感を鍛えることで、正確な音程で歌唱する力が向上します。具体的なトレーニング方法として、ピアノやギターなどの楽器を使用し、基準音を聴いた後に別の音を歌う練習が効果的です。
【関連記事】
倍音とは?歌声・楽器の響きをつかさどる音の物理法則をわかりやすく解説 – ボイトレならNAYUTAS(ナユタス)
そうほう【奏法】
楽器の演奏方法や、技術を指す音楽用語です。各楽器には独自の奏法があり、適切な奏法を習得することで、表現力や演奏技術が向上します。
ボイトレにおいても、正しい発声法や呼吸法といった「奏法」を学ぶことが重要です。これにより、声帯への負担を軽減し、持続的で安定した歌唱が可能となります。
そうるみゅうじっく【ソウルミュージック】

1950年代末頃からアメリカの黒人コミュニティで生まれた音楽ジャンルで、ゴスペルやリズム・アンド・ブルース(R&B)を基盤とし、感情豊かな表現が特徴です。その後、多くの音楽スタイルに影響を与え、世界的に広まりました。
ボイトレにおいては、ソウルミュージックの歌唱を通じて、感情表現やリズム感、独特のフィーリングを養えます。また、特有の発声法やビブラート、フェイクなどの技術を習得することで、表現力豊かな歌唱が可能となるでしょう。
【おすすめ記事】
丸サ進行(Just The Two of Us進行)とは?都会的でクールな循環コードの秘密
そくどひょうご【速度標語】
音楽の速度を指示する記号を指します。たとえば、アレグロ(速く)、アダージョ(ゆっくりと)などです。楽譜上で、演奏のテンポを示すために使用されます。
ボイトレにおいては、速度標語の理解は、楽曲の適切なテンポでの練習や表現に直結します。各速度標語の意味を把握し、その感覚を身につけることで、より正確で表現力豊かな歌唱が可能となるでしょう。
そすてぬうとぺだる【ソステヌート・ペダル】
ピアノの中央に位置するペダルを指し、特定の音を持続させるために使用されます。主に現代音楽やクラシックなどで、効果的に活用されるツールです。
ボイトレにおいては、直接的な関係は少ないものの、ピアノ伴奏者との共演時にソステヌート・ペダルの効果を理解しておけば、より一体感のある演奏が可能です。また、音の持続や響きの感覚を養う上で参考になるでしょう。
そなたけいしき【ソナタ形式】
古典派音楽で多用される構成形式のひとつです。主に提示部、展開部、再現部の三部から成り、主題の提示とその発展、再現を通じて、音楽的な緊張と解決を生み出します。
ボイトレにおいては、ソナタ形式の理解は、クラシック音楽の構造を把握し、楽曲解釈や表現力を高める上で重要です。特に、歌曲やアリアの練習において、この形式の知識が役立つでしょう。
【関連記事】
そふとぱれっと【ソフトパレット】
ソフトパレット(軟口蓋)は、口腔内の奥に位置する柔らかい部分を指し、発声時の共鳴や音色に影響を与えます。特に高音域の発声や鼻腔共鳴に関与しています。
ボイトレにおいては、ソフトパレットのコントロールを習得することで、声の響きや音質を向上させられます。具体的には、軟口蓋を上げる練習を行うことで、共鳴腔が広がり、豊かな音色を得ることが可能です。
そふとぶれす【ソフト・ブレス】
やわらかく音を立てないような感覚で行う、呼吸法の一種です。静かで滑らかな息継ぎを行うことで、歌唱中の不要なノイズを防ぎ、スムーズなフレーズを維持できます。
ボイトレにおいては、ソフト・ブレスの習得により、息のコントロールが向上し、長いフレーズや静かなパッセージでも安定した歌唱が可能となります。特にバラードや繊細な表現が求められる楽曲で効果的です。
そぷらの【ソプラノ】
女性や少年の声域の中で最も高い音域を指します。クラシック音楽では主要なパートのひとつであり、明るく澄んだ音色が特徴です。
ボイトレにおいては、ソプラノの声域を持つ方は高音域の発声練習を重点的に行い、声帯の柔軟性と共鳴を高めることが重要です。また、適切な呼吸法と支えを習得することで、安定した高音を出すことが可能となります。
そり【ソリ】
主に同じ種類の楽器グループによる、ハーモニーを伴った合奏を指します。オーケストラや吹奏楽において、特定のセクションが一体となってメロディーや伴奏を演奏する際に用いられる用語です。
ボイトレにおいては、アンサンブルやコーラスの練習で、ほかの声部や楽器と調和しながら歌う技術を磨くことが重要です。ソリの経験を積むことで、ハーモニー感覚やリズムの一体感が向上し、グループでのパフォーマンス力が高まります。
そりすと【ソリスト】

独奏者を指し、オーケストラやアンサンブルの中で、特定の楽器や声部を担当する演奏者のことです。高い技術と表現力が求められ、楽曲の中心的な役割を担います。
ボイトレにおいては、歌唱のソリストとしてのスキルを磨くことは、独唱やリサイタルでのパフォーマンス向上につながります。自己表現力やステージ上での存在感を高めるための訓練が重要です。
そるふぇえじゅ【ソルフェージュ】
音楽教育の一環として、視唱(楽譜を見て歌う)、聴音(音を聞いて楽譜に書き取る)、リズム練習などを総合的に行う訓練法です。音感やリズム感の向上を目的としています。
ボイトレにおいては、ソルフェージュの練習を通じて、正確な音程やリズム感を養うことができます。これにより、楽譜の読み取り能力が向上し、歌唱の表現力や安定性が高まるでしょう。
そろ【ソロ】
単独で演奏や歌唱を行うことです。オーケストラやバンドの中で、特定の楽器やボーカルが一人で演奏する部分もソロと呼ばれます。
ボイトレにおいては、ソロパートの練習を通じて、自信を持って歌う力や自己表現力を高めることができます。また、ソロ演奏は技術的なスキルだけでなく、感情表現やステージパフォーマンスの向上にも寄与するでしょう。
そろあるばむ【ソロ・アルバム】
特定のアーティストが単独で制作・発表するアルバムのことです。バンドやグループ活動とは別に、個人の音楽性や表現を追求した作品が収録されます。
ボイトレにおいても、ソロ・アルバムの制作は、自身の歌唱力や音楽的アイデンティティを深める機会となります。録音を通じて、細部にわたる表現や技術の向上が図れるでしょう。
そん【ソン】
ソン(son)は、キューバの伝統的な音楽スタイルで、スペインのギター音楽とアフリカのリズムが融合したものです。サルサの前身ともされ、独特のリズムとメロディーが特徴です。
ボイトレにおいては、ソンのリズムや発声法を学ぶことで、ラテン音楽の表現力やリズム感を養えます。多様な音楽ジャンルへの対応力を高めるためにも有益です。
そんぐらいてぃんぐ【ソングライティング】
楽曲の作詞・作曲を行うことを指します。メロディー、ハーモニー、リズム、歌詞など、楽曲の構成要素を創作するプロセスです。
ボイトレにおいても、ソングライティングのスキルを身につければ、自身の感情や経験を歌に反映させ、より個性的な表現が可能となります。また、作詞・作曲の知識は、他者の楽曲理解にも役立ち、歌唱力の向上につながります。
そんご【ソンゴ】
ソンゴ(songo)は、キューバ音楽のリズムパターンのひとつで、1970年代に生まれました。ソンやルンバ、ロックなどの要素を取り入れた複合的なリズムが特徴です。
ボイトレにおいては、ソンゴのリズムを習得することで、リズム感やタイム感の向上が期待できます。特に、ラテン音楽やフュージョンなどのジャンルでの応用が可能です。
【関連記事】
ポップスのリズムの種類とその違いとは?歌唱や演奏、ダンスに役立つ音楽の基礎を解説
そんはちょろ【ソン・ハロチョ】
ソン・ハロチョ(son jarocho)は、メキシコの伝統的な音楽スタイルで、ベラクルス州を中心に発展しました。スペイン、アフリカ、先住民の音楽が融合したもので、明るくリズミカルなサウンドが特徴です。
ボイトレにおいては、ソン・ハロチョのスタイルを学ぶことで、異文化の音楽的要素や発声法を取り入れることができます。これにより、表現の幅が広がり、多彩な音楽ジャンルに対応できるようになるでしょう。
まとめ
ボイトレ用語辞典さ行⑤「そ」は以上です。これらのボイトレ用語を理解し、練習に取り入れていけば、より効果的なトレーニングが行えるでしょう。
次回は、た行①「た」です。お楽しみに!
あなたのボイトレ、歌唱、楽器演奏やダンスに関するスキルアップをNAYUTAS(ナユタス)町田校が応援します。
NAYUTAS町田校では無料体験レッスン受付中‼
ボイスレッスン ボーカルレッスン ダンスレッスン ギターレッスン
現役活躍中の経験豊富な講師陣が、全てマンツーマンでお教えします
「苦手を好きに 好きが得意に」
NAYUTAS町田校SNSリンク