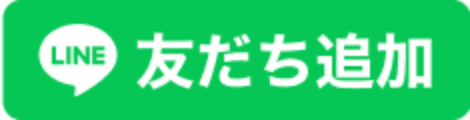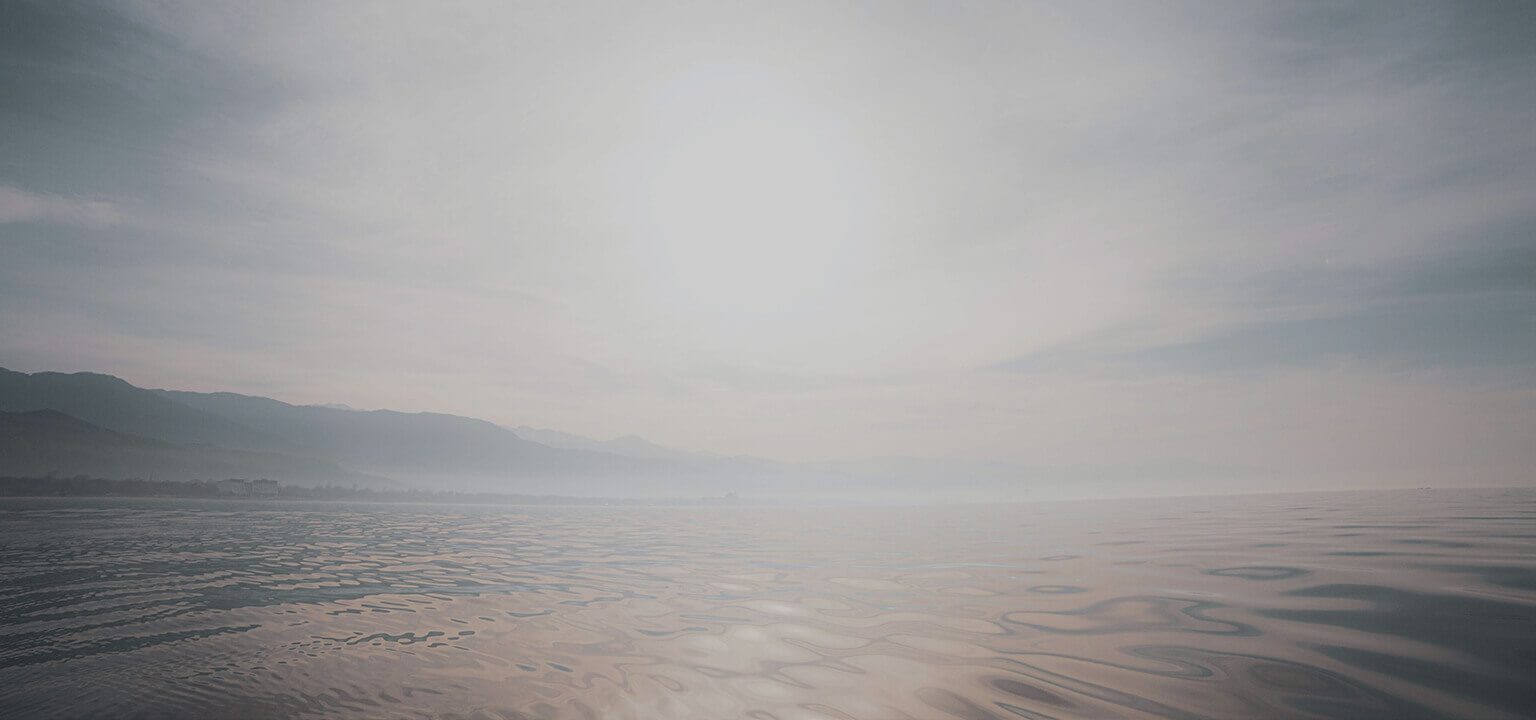こんにちは!NAYUTAS(ナユタス)町田校です。
ボイトレに関連する用語を「ボイトレ用語辞典 〜ナユタス町田校編〜」シリーズとして五十音順で網羅し、わかりやすく解説していきます。
第16回は、た行①「た」です。
【関連記事】
ボイトレ用語辞典 〜ナユタス町田校編〜 #15 さ行⑤「そ」
ボイトレ関連の「た」から始まる用語
ボイトレ関連で「た」から始まる、主な用語の一覧は、次のとおりです。
- たい【タイ】
- たいあっぷ【タイアップ】
- たいいほう【対位法】
- たいこ【太鼓】
- たいしょうごと【大正琴】
- たいせんりつ【対旋律】
- たぎょうかつぜつとれえにんぐ【タ行滑舌トレーニング】
- たくしいむ【タクシーム】
- たじゅうろくおん【多重録音】
- たっち【タッチ】
- たっぴんぐ【タッピング】
- たぽおん【タポーン】
- たぶふ【タブ譜】
- たぶら【タブラ】
- たむ【タム】
- たらんてら【タランテラ】
- たるてぃいにとおん【タルティーニ・トーン】
- たれがそうほう【タレガ奏法】
- たんおんかい【短音階】
- たんご【タンゴ】
- たんちょう【短調】
- たんばりん【タンバリン】
- たんぼりん【タンボリン】
たい【タイ】
タイは、楽譜上で2つの同じ高さの音符を結び、ひとつの音として演奏する記号です。これにより、音符の長さを合計して表現します。
ボイトレにおいては、タイの理解が正確なリズム感の習得に役立ちます。特に、持続音の練習やフレージングの向上に応用できます。
たいあっぷ【タイアップ】
タイアップとは、音楽作品とほかのメディアや商品が連携することを指します。例えば、楽曲がテレビ番組やCM、映画の主題歌として使用されるケースです。
ボイトレにおいては、タイアップされた楽曲を練習することで、最新の音楽トレンドや多様なジャンルに触れることができます。これにより、表現力やレパートリーの幅を広げることが可能です。
たいいほう【対位法】
対位法は、複数の独立した旋律を組み合わせる作曲技法です。各旋律が独立性を保ちながら、同時に調和するように構成されます。
ボイトレにおいては、対位法の知識がハーモニー感覚やアンサンブル能力の向上に役立ちます。ほかのパートと独立しつつ調和するスキルを養うことで、合唱やコーラスでの表現力が高まります。
【関連記事】
たいこ【太鼓】

太鼓は、打楽器の一種で、膜を叩いて音を出す楽器です。日本の伝統音楽や祭りで広く使用され、多様な種類と演奏法があります。
ボイトレにおいては、太鼓のリズムを取り入れた練習がリズム感の向上に効果的です。特に、和太鼓の力強いビートに合わせた発声練習は、腹式呼吸の強化やダイナミックな表現力の習得につながります。
たいしょうごと【大正琴】
大正琴は、日本の伝統的な弦楽器で、大正時代に考案されました。鍵盤を押しながら弦を弾くことで音を出します。
ボイトレにおいては、大正琴の音色や旋律を学ぶことで、日本の音楽的要素を取り入れた表現力を養うことができます。これにより、和のテイストを持つ楽曲の解釈や歌唱に役立ちます。
たいせんりつ【対旋律】
対旋律とは、主旋律に対して補完的に奏でられる旋律のことです。ハーモニーを豊かにし、楽曲に深みを与えます。
ボイトレにおいては、対旋律を意識した練習が、ハーモニー感覚やアンサンブル能力の向上につながります。ほかのパートとの調和を意識することで、より豊かな音楽表現が可能となります。
たぎょうかつぜつとれえにんぐ【タ行滑舌トレーニング】
タ行滑舌トレーニングとは、「たちつてと」の発音を明瞭にするための練習方法です。具体的には、「たちつてと」「ちつてとた」などの音節を繰り返し発音し、舌の位置や動きを意識することで滑舌を改善します。
ボイトレにおいては、タ行の発音練習が明瞭な歌唱に直結します。特に、日本語の歌詞ではタ行の音が頻出するため、これらのトレーニングを取り入れることで、歌詞の伝達力を高めるのに有効です。
たくしいむ【タクシーム】
タクシームは、中東音楽における即興演奏を指します。主に弦楽器や管楽器で行われ、演奏者の感情や技術を自由に表現する場となります。
ボイトレにおいては、タクシームの概念を取り入れることで、即興的な表現力や創造性を養えます。即興でメロディを紡ぐ練習は、音楽的な柔軟性や感性の向上に役立つでしょう。
たじゅうろくおん【多重録音】
多重録音とは、すでに録音した音声や演奏に対して、新たな音を重ねて録音する技術です。この手法により、一人の演奏者が複数のパートを演奏し、重ね合わせて豊かな音楽を作り上げることが可能となります。
ボイトレにおいては、多重録音で自身の声を重ねて録音すれば、コーラスワークのスキル向上や、客観的な分析に役立つでしょう。また、録音を重ねる過程で、リズム感や音程の正確さを確認し、改善できます。
たっち【タッチ】

タッチは、鍵盤楽器や弦楽器での指の触れ方や力加減を指します。演奏のニュアンスや音色に、大きく影響する要素です。
ボイトレにおいては、直接的な関係は少ないものの、タッチの概念を理解することで、声のニュアンスや表現力の幅を広げるヒントとなります。微妙な力加減やアーティキュレーション(滑舌)を意識すれば、歌唱の質が向上するでしょう。
たっぴんぐ【タッピング】
タッピングは、ギター演奏における奏法のひとつで、指板上の弦を(特に右の)指で叩き付けて押弦したり横に弾いたりして音を出す技法です。「ライトハンド奏法」とも呼ばれ、エレキギターで多用されます。
ボイトレにおいては、ギター伴奏を伴う歌唱において、タッピング奏法を理解することで、伴奏者とのコミュニケーションが円滑になり、演奏全体の表現力を高めることができます。
たぽおん【タポーン】
タポーンは、タイの伝統的な太鼓で、両端が細く中央が膨らんだ形状をしています。手やスティックで叩いて演奏する、タイの伝統音楽や舞踊で使用される楽器です。
ボイトレにおいては、タポーンのリズムを学ぶことで、東南アジア特有のリズム感覚を身につけることができます。これにより、アジアの音楽ジャンルにおける表現力を高めることが可能です。
たぶふ【タブ譜】
タブ譜は、ギターなどの指板楽器のための特殊な楽譜表記法で、正式にはタブラチュアと呼ばれます。数字や記号で指の位置や運指を示します。
ボイトレにおいては、タブ譜の理解がギター伴奏を伴う歌唱に役立ちます。自らギターを演奏しながら歌う際、タブ譜を活用することで、効率的に練習を進めることができます。
たぶら【タブラ】
タブラは、インドの伝統的な打楽器で、大小二つの太鼓から構成される楽器です。手のひらや指を使って複雑なリズムを奏で、クラシック音楽や現代音楽など幅広いジャンルで使用されます。
ボイトレにおいては、タブラのリズムパターンを学ぶことで、リズム感や拍子感の強化につながります。特に、インド音楽やフュージョン音楽を歌う際に、そのリズムの特徴を理解し、表現力を高めることが可能です。
たむ【タム】
タムは、ドラムセットの一部で、中型の太鼓を指します。トムとも呼ばれ、音程の異なる複数のタムを組み合わせて使用する場合が多く、リズムやフィルインを豊かに彩るのが特徴です。
ボイトレにおいては、タムのリズムパターンを理解することで、リズム感やタイム感の向上が図れます。特に、バンドでの歌唱時にドラムのフィルインを意識することで、楽曲のダイナミクスや展開をより深く理解し、歌唱表現に反映させることができます。
たらんてら【タランテラ】
タランテラは、イタリアの伝統的な速いテンポの舞曲です。元々は毒蜘蛛の毒を治療するための踊りとされ、活気あるリズムと明るいメロディーに特徴があります。
ボイトレにおいては、タランテラの楽曲を練習することで、速いテンポでの発声やリズム感の向上が期待できます。また、明るく軽快な表現力を養うことにも役立つでしょう。
たるてぃいにとおん【タルティーニ・トーン】
タルティーニ・トーン(Tartini Tone)は「差音」とも呼ばれる、2つの音を同時に鳴らしたときに生じるうねりのような音です。イタリアの作曲家ジュゼッペ・タルティーニ等が発見した現象で、和音の研究や調律において重要な概念とされています。
ボイトレにおいては、タルティーニ音の理解が、和音の構造や音程感覚の向上に役立ちます。特に、ハーモニーを意識した歌唱やコーラスワークにおいて、ほかの声部との調和を深めるために重要な知識となるでしょう。
【関連記事】
倍音とは?歌声・楽器の響きをつかさどる音の物理法則をわかりやすく解説 – ボイトレならNAYUTAS(ナユタス)
たれがそうほう【タレガ奏法】
タレガ奏法とは、スペインのギタリスト、フランシスコ・タレガ(1852~1909)によって確立されたクラシックギターの奏法です。彼は現代のギター奏法の基礎を築き、多くの優れた小品を残しました。
ボイトレにおいては、タレガ奏法の理解がギター伴奏を伴う歌唱に役立ちます。特に、ギターの音色や奏法を知ることで、伴奏との一体感を高め、表現力豊かな歌唱を実現できます。
たんおんかい【短音階】
短音階は、全音と半音の特定の並びを持つ音階で、哀愁や悲しみを表現する際に用いられます。自然短音階、和声短音階、旋律短音階などの種類があります。
ボイトレにおいては、短音階の練習が、音階感覚や表現力の向上につながるでしょう。特に、感情豊かな歌唱を目指す際に、短音階の理解と活用が重要となります。
たんご【タンゴ】

タンゴは、アルゼンチン発祥の音楽とダンスのスタイルで、19世紀後半にブエノスアイレスの港町ラ・ボカ地区で生まれました。当時、ヨーロッパからの移民やアフリカ系住民、先住民など多様な文化が交わり、独特の音楽と踊りが形成されています。
ボイトレにおいては、タンゴのリズムや情感を取り入れることで、リズム感や表現力の向上が期待できるでしょう。特に、タンゴ特有の情熱的で哀愁を帯びたメロディーを歌唱練習に活用すれば、感情表現の幅を広げられます。
【関連記事】
ポップスのリズムの種類とその違いとは?歌唱や演奏、ダンスに役立つ音楽の基礎を解説
たんちょう【短調】
短音階を基にした調性で、哀愁や悲しみ、深い感情を表現する際に用いられます。メジャーキー(長調)に対して、マイナーキーと呼ばれます。
ボイトレにおいては、短調の楽曲を練習することで、感情表現の幅を広げることが可能です。特に、悲しみや切なさを表現する際の声の使い方やニュアンスを習得するのに役立ちます。
【おすすめ記事】
丸サ進行(Just The Two of Us進行)とは?都会的でクールな循環コードの秘密
たんばりん【タンバリン】
タンバリン(別名タンブリン)は、小さな打楽器で、枠に取り付けられたジングル(小さな金属製のシンバル)を持ち、手で叩いたり振ったりして音を出します。ポピュラー音楽やクラシック音楽など、さまざまなジャンルで使用される楽器です。
ボイトレにおいては、タンバリンを用いたリズム練習が、リズム感の向上に効果的です。シンプルな構造ながら、多彩なリズムパターンを生み出すことができ、歌唱時のリズムキープやタイミングの習得に役立ちます。
たんぼりん【タンボリン】
タンボリンは、ブラジルの小型の打楽器で、片面に膜を張った小さなフレームドラムです。たとえばサンバのダンサーが踊りながらスティックで叩き、高音域のリズムを担当します。
ボイトレにおいては、タンボリンのリズムを取り入れた練習が、リズム感やテンポ感の向上に効果的です。特に、サンバやボサノバなどのブラジル音楽を歌う際に、その独特のリズムを体得するのに役立ちます。
まとめ
ボイトレ用語辞典た行①「た」は以上です。これらのボイトレ用語を理解し、練習に取り入れていけば、より効果的なトレーニングが行えるでしょう。
次回は、た行②「ち」です。お楽しみに!
あなたのボイトレ、歌唱、楽器演奏やダンスに関するスキルアップをNAYUTAS(ナユタス)町田校が応援します。
NAYUTAS町田校では無料体験レッスン受付中‼
ボイスレッスン ボーカルレッスン ダンスレッスン ギターレッスン
現役活躍中の経験豊富な講師陣が、全てマンツーマンでお教えします
「苦手を好きに 好きが得意に」
NAYUTAS町田校SNSリンク