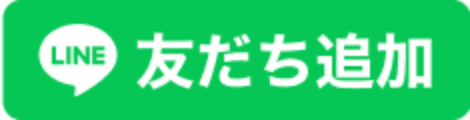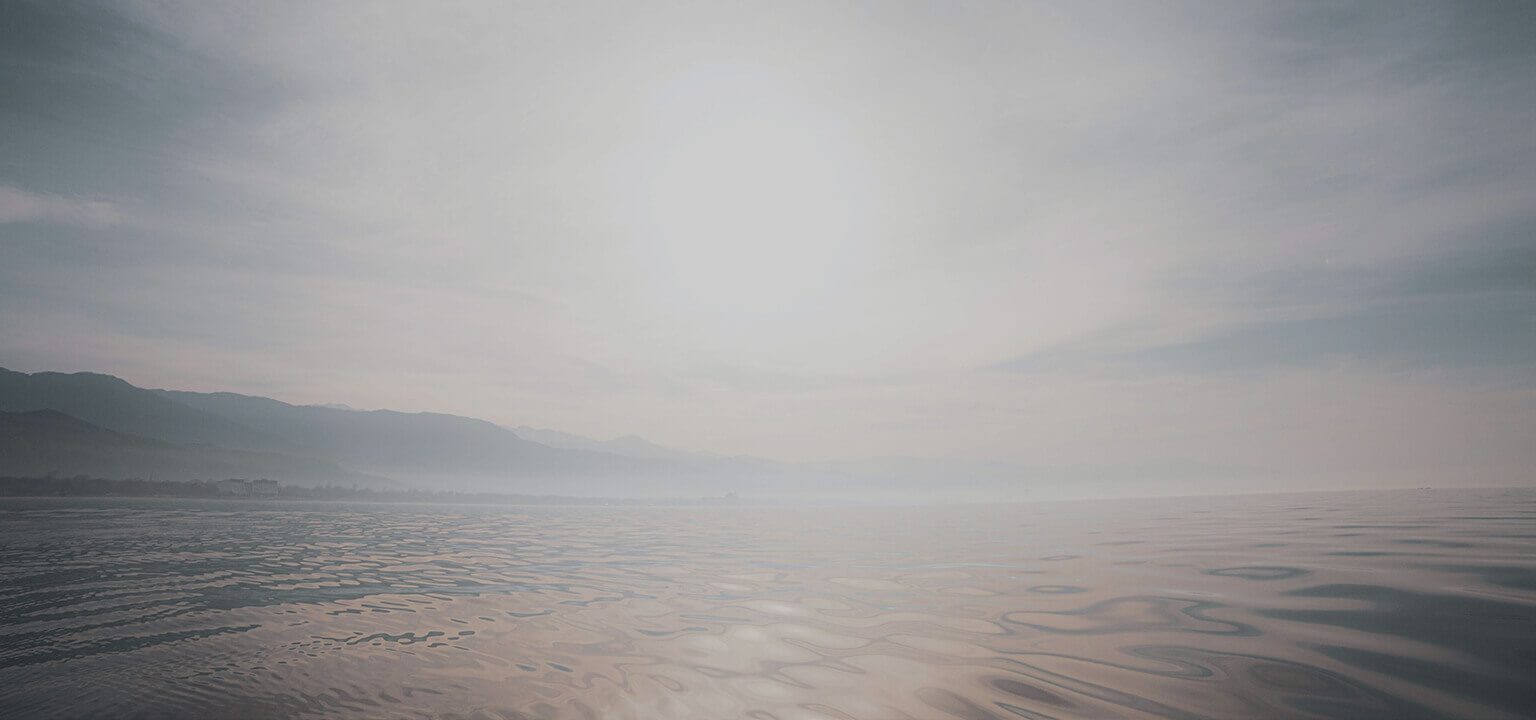こんにちは!NAYUTAS(ナユタス)中野校です。
演歌をかっこよく歌いたいと思っても、「こぶしってどうするの?」「演歌らしい響きが出ない」と悩む人は多いものです。
演歌は独特のテクニックと深い感情表現が求められるジャンルですが、ポイントを押さえれば初心者でも上達できます。
この記事では、演歌の歌い方の基本から具体的な練習方法、おすすめの練習曲まで徹底解説します。
目次
演歌が難しいと言われる理由とは?
まずは、なぜ演歌が難しいジャンルと言われるのかを理解し、歌い方のコツをつかみやすくしましょう。
1. メロディの揺れや抑揚の作り込みが必要
演歌の最大の特徴は、メロディの細かな揺れと大きな抑揚です。ポップスのように一定のリズムで歌うのではなく、歌詞の情景に合わせて強弱や間をつけて歌うため、フレーズごとの緩急が非常に重要になります。ただ音程をなぞるだけでは演歌らしさが出ず、感情に合わせた“揺れ”を作り込む必要があるのです。
2. 歌詞の情景や感情表現が求められる
演歌は「人生」「別れ」「故郷」といった深いテーマを扱うことが多く、歌詞の意味をどれだけ理解して表現できるかが完成度を大きく左右します。歌詞を情景としてイメージし、それを声や表情に乗せて表現することが欠かせません。
3. 発声の安定とロングトーンの技術が不可欠
演歌は、語尾を長く伸ばしながら揺らしたり、太く安定した声を保ったまま歌ったりする場面が多くあります。特にロングトーンは腹式呼吸と喉の開きが不十分だと、すぐに音が揺れたり息が続かなくなってしまいます。発声の土台がしっかりしているかどうかが、力強さに直結します。
おすすめ記事
声量を鍛えるトレーニング方法|ボーカルが劇的に変わる練習法とコツ
演歌の歌い方をマスターする5つのポイント

演歌は、特別な技術や才能がないと歌えないと思われがちですが、コツを知っているかどうかが上達の分かれ道です。初心者でもすぐ取り入れられる、基本のテクニックを紹介します。
1. こぶしは“揺らす”のではなく“音を回す”
こぶしは「音程を細かく上下させる」技術ですが、力任せに声を揺らすものではありません。1つの音を中心に“くるり”と回すイメージで音を動かします。
- 「あー」を1音だけ上下に動かす
- 「花」「酒」など短い日本語で試す
- フレーズの語尾に少しだけ入れてみる
焦らず少しずつ慣らすことで自然なこぶしに近づきます。
2. ビブラートは横揺れではなく細かく縦に揺らす
ポップスのビブラートは音程が横に揺れるような印象ですが、演歌は細かく縦に揺らすのが特徴です。音を大きく動かさず、喉と息のコントロールで細かい波を作ります。
- 5秒ほどロングトーンを出し、息を軽く揺らす
- 揺れの幅を狭くしながら安定させる
自然なビブラートを目指すと演歌の雰囲気がぐっと増します。
3. 息の量と音量で抑揚をつける
演歌の抑揚は声の大きさだけでなく、息の量を調整することで生まれます。語りかけるように息を多めに使う部分と、力強く響かせる部分のコントラストが重要です。
- サビに向けて徐々に声量を上げる
- 語り部分は息多めでやさしく
- 語尾を抜くか残すかで雰囲気を変える
抑揚のつけ方ひとつでドラマチックさが大きく変化します。
4. 鼻腔と喉を響かせて力強さを出す
演歌特有の“太い声”を出すには、鼻腔と喉の両方がしっかり響いている必要があります。喉を締めずリラックスした発声で、胸〜顔の前方に響きを感じるのが理想です。
- 軽く鼻にかける意識で「あんー」と響きを作る
- 口を縦に開き、喉の奥を広げる
- 響きが前に抜ける感覚をつかむ
ロングトーンが安定しやすくなり、演歌らしい深みのある声になります。
5. 歌詞の情景をイメージして感情を表現する
演歌の肝は感情表現です。どんなにテクニックがあっても、歌詞の情景や人物像をイメージできていなければ心に響きません。
- 歌詞の主人公はどんな気持ちか
- 風景や時間帯はどうか
- どんな物語を語っているのか
これを頭に描きながら声に乗せることで、自然に抑揚や間の取り方が変わり、歌にドラマが生まれます。
NAYUTAS(ナユタス)中野校では、プロのボーカル講師が一人ひとりの歌い方の弱点を見抜いたうえで、目標やペースに合わせて丁寧に指導を行っています。
初心者の方も安心の完全マンツーマンレッスンで、モチベーションを維持しながら最短で上達を目指せます!
今日からできる!演歌が上手くなる実践トレーニング

基礎テクニックを理解したら、次は実践的な練習でさらに磨きをかけましょう。毎日手軽にできるものから、本格的なスキルアップにつながる練習法まで紹介します。
1. 腹式呼吸と息のコントロールを鍛える練習
演歌の基礎は腹式呼吸です。息が安定すればロングトーンや抑揚も思いのままになります。
- 仰向けになり、お腹を膨らませて吸う練習
- 4秒吸って8秒吐く呼吸法
- ロングトーンで息の量を均等に保つ練習
これを毎日数分続けるだけで、声の安定感が変わるでしょう。
2. ワンフレーズ反復でこぶしを安定させる練習
こぶしは力技ではなく、積み重ねで身につく技術です。
- 1つのフレーズをゆっくり歌う
- 語尾の音を少しだけ上下させてみる
- 無理に入れず「自然に転がす」感覚を大切にする
慣れてくると、こぶしを入れるべき場所と入れない場所が感覚的に分かるようになります。
3. 語尾の表現力を鍛える練習
演歌は語尾の印象で歌全体の雰囲気が決まると言っても過言ではありません。
- 語尾を「切る」「抜く」「残す」をそれぞれ練習
- フレーズごとに語尾のニュアンスを変えて表現の幅を広げる
- ロングトーンを使って語尾を伸ばす練習も効果的
語尾の処理が丁寧になると、演歌の完成度が一気に上がります。
4. ビブラートを自然につける練習
ビブラートはかけようとするのではなく、自然に出るのが理想です。
- ロングトーンを一定に伸ばす練習
- 息を軽く揺らして振動を作る
- 揺れ幅を小さくし、細かい波を意識
安定したビブラートが加わることで、演歌らしい味わいが出てきます。
おすすめ記事
カラオケで低い声が出ない…を解決!低音を出すコツとおすすめ練習曲10選
初心者におすすめの演歌曲8選
初心者でも歌いやすく、かつ演歌の魅力がしっかり味わえる曲を厳選して紹介します。練習しながら演歌の表現力を高めるのにぴったりです。
きよしのズンドコ節 / 氷川きよし
明るいテンポで難易度も低めの曲です。演歌に苦手意識がある人でも、楽しみながらこぶしやビブラートを練習できます。
北の漁場 / 北島三郎
力強く勢いのある曲で、こぶしの練習に最適です。強弱のつけやすいメロディなので、演歌らしさを身につけたい初心者におすすめです。
津軽海峡・冬景色 / 石川さゆり
女性演歌の代表的な一曲です。抑揚の付け方や情景描写の表現が重要で、感情を乗せる練習に非常に向いています。
また君に恋してる / 坂本冬美
柔らかなビブラートと息遣いが求められ、演歌が初めての人でも取り組みやすいバラード調の一曲です。
長良川艶歌 / 五木ひろし
琴の音色と歌い上げの融合が魅力の一曲。息遣いや語尾処理の練習に向いており、感情表現を磨くのにぴったりです。
兄弟船 / 鳥羽一郎
重厚感のある曲で、胸の響きを使いながら歌う練習にぴったりです。低音の安定とロングトーンの強さが鍛えられます。
舟唄 / 八代亜紀
深い低音を要求されるため、発声の安定を鍛えたい人にぴったりです。語尾の処理や響きの練習にも向いています。
人生いろいろ / 島倉千代子
明るさと切なさが同居する演歌の名曲。歌詞の情景をイメージしながら歌う練習に最適です。
まとめ
演歌は難しいと感じる人が多いものの、こぶし・ビブラート・抑揚といった技術を段階的に身につければ必ず上達します。
さらに、歌詞の情景や感情をしっかりとイメージすることで、ぐっと深みが増すでしょう。
紹介したポイントを参考に、演歌ならではの“語る歌”をぜひ楽しんでみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
NAYUTAS中野校では、初心者からプロ志望まで、楽しく本気でレッスンしています。
気になる方はぜひ一度、体験レッスンにお越しくださいね😊
📍中野駅北口から徒歩2分| 無料体験レッスン受付中 → 詳細はこちら