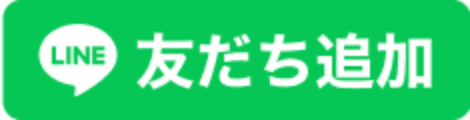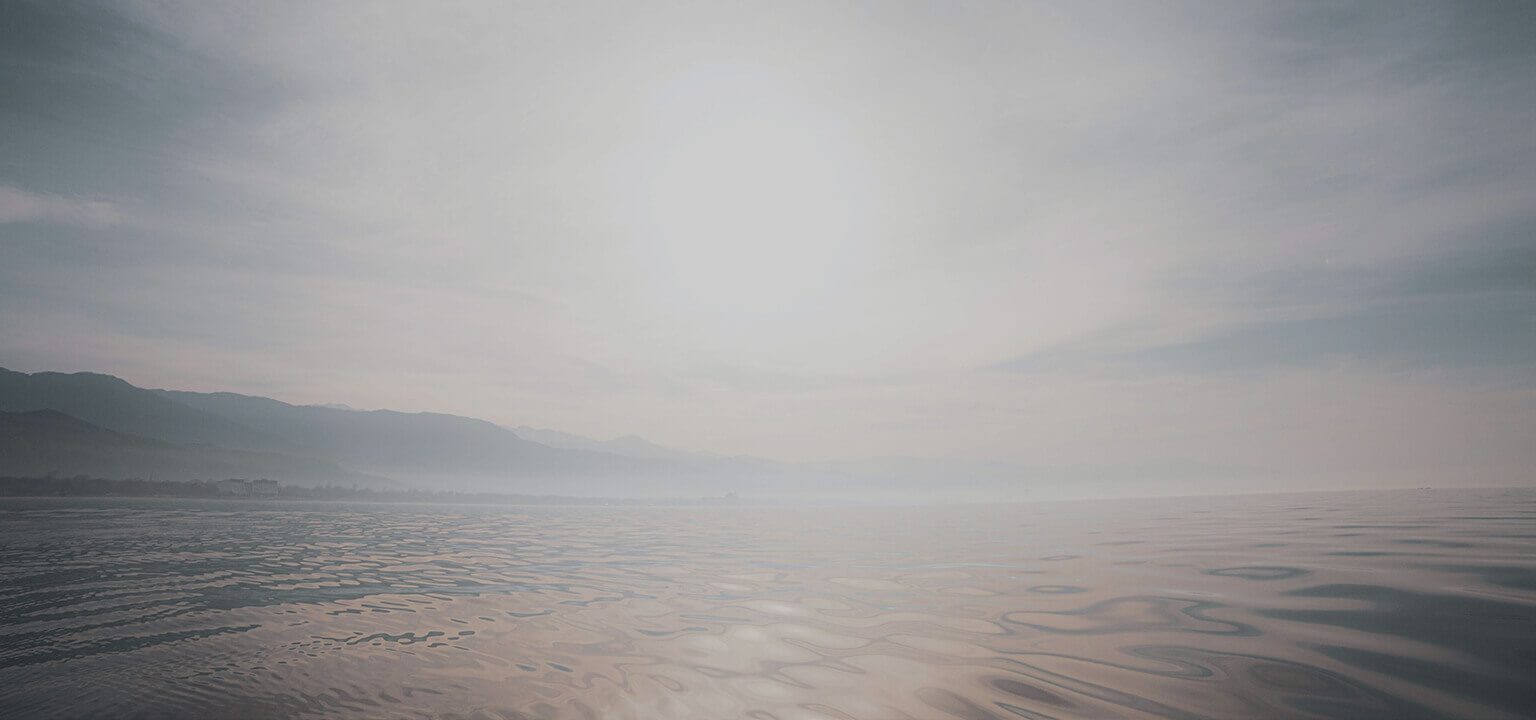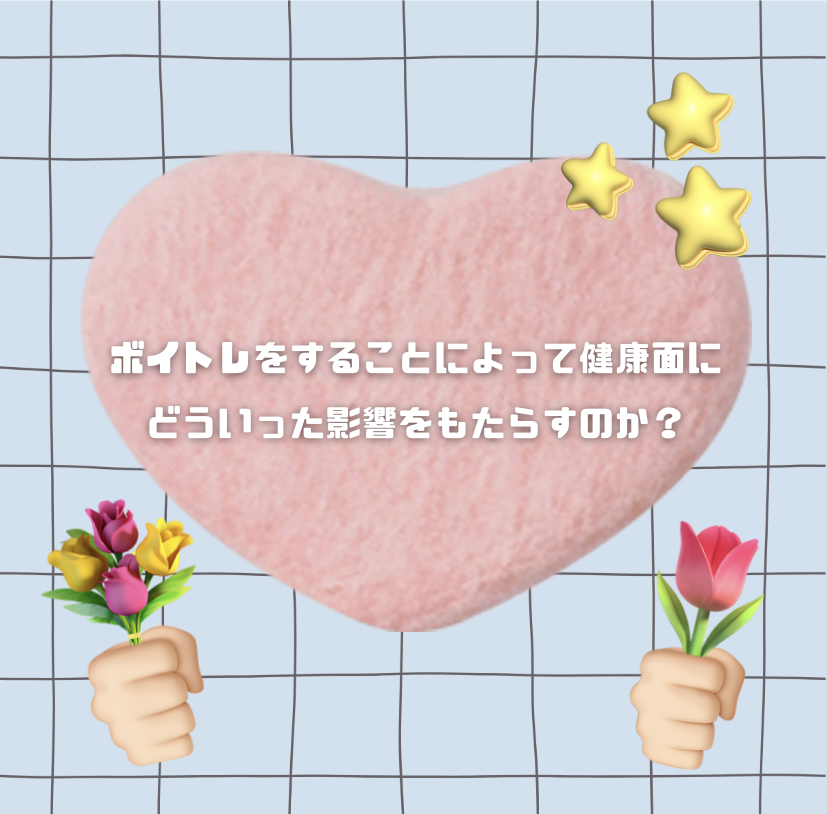みなさんこんにちは!😺
NAYUTAS横浜駅前校です!🍀⭐︎
今回はボイトレをすることによって健康面にどういった影響をもたらすのかについてお話しします!
はじめに:ボイトレとは何か、その基本的な目的
ボイトレとは、「声を鍛えるトレーニング」「発声練習」のことを指し、歌唱力、滑舌、声量、表現力といったスキルを高めることが目的です。プロの歌手や声優、アナウンサーを目指す方々だけでなく、日常的に人前で話す機会のある方、滑舌に不安のある方、声そのものの健康維持や改善を目指す一般の方にも取り入れられています。
ここでは、まず「身体的健康」「精神的・心理的健康」「生活習慣や社会的側面」の3つ観点に分けて、ボイトレがもたらす実際の影響を整理してご紹介していきます。
1. 深呼吸を習慣化し、肺を鍛える
ボイトレの多くは、まず「横隔膜呼吸」や「腹式呼吸」を重視しています。私たちが普段している胸式呼吸でなく、腹部に空気を入れて「息を使う」感覚を身につけることで、様々な効果が現れます。
-
肺活量の増加:深く長く、安定した呼吸が可能になり、肺が拡張・収縮する習慣がつくことで肺機能が強化されます。
-
胸郭・肋間筋の柔軟性向上:胸郭周りの筋肉がほぐれ、呼吸時の筋肉疲労が減り、呼吸そのものが楽になります。
-
姿勢の改善:呼吸を意識する中で自然と背筋が伸び、姿勢が整っていきます。これは呼吸効率を高めるだけでなく、肩こりや首の緊張軽減にもつながります。
このような呼吸器系への良い影響は、普段の呼吸の質を高め、疲れにくくなる、酸素取り込みが上手になるといった体感的なメリットもあります。
2. 発声機能の向上により、喉・声帯の健康につながる
ボイトレでは「喉を締めずに声を出す」「柔らかく響く声を出す」といった技術が重視されます。これによって、以下のような効果が現れます。
-
声帯の過緊張を防ぐ:無理な高音や張り上げによる負担が減り、声帯が疲れにくくなります。
-
喉の可動域・柔軟性の向上:高音・低音をスムーズに使う練習で、声帯を含めた喉全体の筋肉が柔らかくなり、声の安定性が増します。
-
声の響き・共鳴の効率化:無駄な力みを取った発声により、響きを使った声の伝達が可能になり、ボリュームを必要以上に出す必要がなくなります。これは声帯の保護にもつながります。
-
声枯れ・喉のトラブルの減少:発声の質が上がることで喉への負担を軽減でき、声枯れや炎症、ポリープなどのトラブルが起きにくくなります。
このように、発声の技術習得=声帯ケアの習慣化、とも言えます。声の出し方が変わると、結果的に喉の健康にも良い効果が生まれます。
3. 姿勢・筋肉バランスへ働きかけ、体全体の安定と疲労防止につながる
ボイトレは呼吸と密接に結びついているため、自然と「姿勢」に目が向きます。具体的には、以下のような効果が現れます。
-
体幹の意識と強化:発声時に使う腹横筋や内腹斜筋、背筋など、体幹の筋肉が自然に使われ、姿勢を支える筋力がついてきます。
-
肩・首・背中の緊張軽減:力まず自然な姿勢で声を出す習慣により、首や肩の無駄な力が抜けるようになります。これは肩こりや首のこり、頭痛の軽減にも効果があります。
-
立ち姿・座り姿の改善:猫背による胸郭の圧迫が改善され、逆に胸を開いた姿勢に。この姿勢変化は呼吸効率の向上にもつながります。
姿勢の改善は、日常生活での疲れにくさや、デスクワーク・スマホの見過ぎなどによる慢性的な体のこわばりにも良い影響を与えます。
4. 自律神経・ストレスケアへの寄与で現れるリラックス効果
発声練習や歌唱には、呼吸としっかり連動した「リズム」があります。このリズム感を伴う練習がもたらす効果として以下のような効果があります。
-
副交感神経の活性化:深くゆっくりした呼吸や声を出す行為は、ストレスホルモン(コルチゾールなど)の分泌を抑え、心身ともにリラックス状態へ導きます。
-
集中力の向上:音程・リズム・声の出し方に注意が向くことで「今ここ」に集中でき、マインドフルネス的な効果も得られます。
-
ストレス開放効果:自ら声を出すことで、感情の発散や表現欲求の解放が起こり、精神的なストレスや緊張が和らぎます。
実際に、カラオケや歌唱後に気持ちがすっきりした、という体験を誰もがしたことがあると思いますが、これこそが音や声による“精神的なリセット”の効果です。
5. 自己表現の確立と自信の向上
声はコミュニケーションの要です。声の改善がもたらす精神・心理面での効果としては以下のような効果があります。
-
自己表現の自信:はっきりと、響きのある声で話せるようになると、自己表現への自信が増し、人前で話す怖さや緊張が軽減されます。
-
コミュニケーションの円滑化:滑舌や発声が整うことで、相手に伝わりやすくなり、誤解やストレスの少ない会話が可能になります。
-
自己肯定感の向上:声の改善は“自分の印象”にも直結します。声に満足できることが自己肯定につながり、人との関わりに積極性が生まれます。
-
表現力の幅が広がる:声の強弱、色(トーン)、リズムを自由に使いこなせるようになると、感情やニュアンスを豊かに表現でき、創作活動やプレゼンなどの場面でも自分を自在に表現できるようになります。
こうした心理的効果は、仕事や学業、日常生活で自然と前向きな変化を生み出してくれます。
6. 継続・学び・コミュニケーションの場の創出
ボイトレを継続する中で生まれる、外部との接点や習慣の変化にも注目しましょう。
-
継続習慣の構築:毎日少しずつでも声を出す時間を持つことで、自己管理能力・継続力が養われます。
-
学びの楽しさ:発声の仕組みや声の種類など、“知識としての発見”が自分を深める喜びにつながります。
-
コミュニティとの交流:ボイトレ教室やオンラインサロン、カラオケでの仲間との交流を通じて、気軽に相談できる居場所やモチベーションの維持が可能です。
-
多様な活動への応用:カラオケ、朗読、演劇、スピーチ、プレゼン、歌声配信といった活動の幅が広がり、趣味の充実やキャリアの可能性も高まります。
こうした社会的な側面は、健康の“行動面”“モチベーション面”で大きなプラスになり、声と健康との関係を支えます。
7. 日常に取り入れる方法と効果
では、実際どのようにボイトレを日常に取り入れて健康効果を享受できるのか、具体的な「習慣化アイデア」と「実践の効果」例を見てみましょう。
習慣化アイデア
-
毎朝「声出しルーティン」:朝起きたらガラガラ声でも構わないので、「あ〜」「い〜」「う〜」と簡単な母音発声を10回ずつ。呼吸と声のスイッチを一日に入れる習慣になります。
-
ランチ後や仕事の合間に「滑舌体操」:例えば「パピプペポ」「ナニヌネノ」など母音と子音を組み合わせた早口言葉を音読。舌や口まわりの筋肉がほぐれ、口の動きが軽やかになります。
-
寝る前に「声・呼吸メンテ」:大きく息を吸って、細く長く「はぁ〜」と吐く。これだけで自律神経が落ち着き、質の良い睡眠を促します。
-
週末に「歌唱タイム」:好きな曲を歌うことで、楽しみながら発声練習し、ストレス発散にもなります。
まとめ:ボイトレがもたらす健康へのトータルな恩恵
ボイトレは単なる“声を良くする練習”に留まらず、以下のような幅広い健康効果が期待できる“全身的なトレーニング”です。
| 分野 | 主な効果 |
|---|---|
| 呼吸・肺機能 | 肺活量アップ、呼吸効率改善、姿勢改善 |
| 発声機能 | 声帯の健康維持、喉の柔軟性向上、声枯れ防止 |
| 筋肉・姿勢 | 体幹強化、肩こり・首こり軽減、姿勢改善 |
| 自律神経・メンタル | リラックス促進、集中力向上、ストレス軽減 |
| 精神・心理 | 自信・自己肯定感アップ、コミュニケーション改善、表現力強化 |
| 習慣化・社会 | 継続力・自己管理力アップ、学び・交流の場の創出、活動の幅拡大 |
声を変えることで、自分自身の体や心、さらには社会との関わり方も変化させる力があります。「声をもっと良くしたい」と思ったその一歩は、健康という大きな広がりにつながります。
毎日のほんの数分のトレーニングで、体と心が変わっていく実感を味わってみましょう!
🫧横浜駅からアクセス抜群の魅力あふれる教室で、楽しくボイトレ・マンツーマンダンス始めてみませんか??🫧
「聞き手の心に響く歌を歌いたい・・・」
「オーディション対策がしたい・・・」
どんな方でも、プロフェッショナル講師がしっかりとサポートするNAYUTASなら安心してご受講いただけます。
まずは無料体験レッスンのお申込みをお待ちしております!
//
横浜ででボイトレ!ダンス!
「苦手を好きに、好きが得意に」
ボイトレ・マンツーマンダンスなら W受講も可能なNAYUTAS横浜駅前校へ!
\\
⇒体験レッスンのお申込みはこちらをクリック🎤✨